〜交感神経優位がもたらす体のサインの鈍化と対策〜
はじめに
夏場になると、熱中症は誰にとっても注意が必要な健康リスクですが、特にストレス過多な人は要注意です。
日々の仕事や人間関係、生活環境によって交感神経が優位な状態が続くと、本来であれば「暑い」「のぼせる」「だるい」などの体の警告サインを感じにくくなります。
これは、体温調節や発汗のシステムが自律神経の影響を強く受けているためです。自分では「大丈夫」と思っていても、実は体内では熱がこもり始めているケースが少なくありません。
本記事では、自律神経と熱中症の関係、東洋医学から見たストレスと熱の関係、さらに当院の施術による改善アプローチについて詳しくご紹介します。
1. ストレスと交感神経優位がもたらす熱中症リスク
自律神経には、活動を司る交感神経と、休息や回復を促す副交感神経があります。
ストレス過多な人は交感神経が過剰に働き、心拍数の増加・血圧の上昇・筋肉の緊張が続く一方で、体のセンサーが鈍くなります。
特に夏場は以下のようなリスクが生じます。
- 暑さを感じにくい:温度感覚の伝達が鈍り、体温上昇に気づきにくい。
- 喉の渇きを感じにくい:水分不足でも飲水行動が遅れる。
- 発汗機能の乱れ:必要な時に汗が出ない、逆に過剰に出るなどの不均衡。
- 血流の偏り:脳や心臓への血流を優先し、末端や皮膚での放熱が滞る。
この状態が続くと、気づかないうちに熱中症の初期段階(軽度脱水、熱疲労)を経て、中等度〜重度へと進行する危険性が高まります。
2. 自律神経の観点から見たメカニズム
交感神経優位は「戦うか逃げるか」の緊張モードであり、生命維持のために瞬間的な対応は得意ですが、長時間続くと体の恒常性(ホメオスタシス)を崩します。
- 発汗中枢の反応低下
脳の視床下部にある体温中枢がストレスホルモン(コルチゾールやアドレナリン)の影響を受け、感度が鈍くなります。 - 末梢血管の収縮
皮膚の毛細血管が収縮して熱放散が抑えられ、体内熱がこもる。 - 呼吸パターンの変化
浅く速い呼吸になり、二酸化炭素と酸素のバランスが崩れ、倦怠感や頭痛を引き起こす。
結果として、「暑い・苦しい・だるい」というサインが弱まり、気づいた時には体温が危険域に達していることがあります。
3. 東洋医学から見たストレスと熱の関係
東洋医学では、ストレス過多は**「肝気鬱結(かんきうっけつ)」や「気逆」などの状態を招くとされます。
肝は気血の巡りを司り、感情の変化にも深く関わります。肝気が滞ると「熱」に変化しやすく、これを肝鬱化火**といいます。
さらに、ストレスで交感神経が優位になると「心(しん)」の働きも乱れ、心火(しんか)が亢進します。これにより体内に余分な熱がこもり、頭部のほてり・顔の赤み・不眠などが起こります。
東洋医学での代表的な解釈:
- 肝鬱化火:イライラ、頭痛、目の充血、顔の赤み
- 心火上炎:不眠、動悸、口の渇き
- 気血両虚:慢性疲労、水分代謝低下でむくみや冷えも併発
熱中症の初期段階であっても、東洋医学的には「熱」と「水(津液)」のバランスが崩れている状態として捉えます。
4. 当院の施術アプローチ
くろちゃん鍼灸整体院では、ストレス過多による交感神経優位と熱こもりの両面にアプローチします。
骨盤矯正
骨盤の歪みは全身の血流と神経伝達を阻害します。骨盤を正しい位置に整えることで、下肢から心臓への血流がスムーズになり、熱放散の効率も向上します。
猫背矯正
猫背や巻き肩は胸郭を圧迫し、呼吸を浅くします。当院の猫背矯正では胸郭を広げ、深い呼吸を可能にして酸素交換を改善します。
鍼灸施術
東洋医学に基づき、交感神経の過緊張を和らげるツボ(百会・合谷・内関・足三里など)にアプローチします。鍼刺激で副交感神経を優位にし、体温調節機能の回復を促します。
頭部施術
頭皮や後頭部の筋緊張を緩め、脳への血流を改善します。これにより体温中枢の働きを助け、熱感やのぼせの軽減につながります。
5. 通院目安
- 急性期(熱中症症状や強い倦怠感がある時期):週2回
- リハビリ期(症状が落ち着き、回復を目指す時期):週1回
- メンテナンス期(予防・再発防止):月2〜3回
6. 予約方法
当院では、LINE・ホームページにて24時間予約を受け付けています。
忙しい方でも隙間時間にご予約いただけます。
✅ LINE・ホームページから24時間予約受付中
今すぐご予約はこちらから!相談も予約もLINEでのご連絡が便利です!
📱LINE![]()




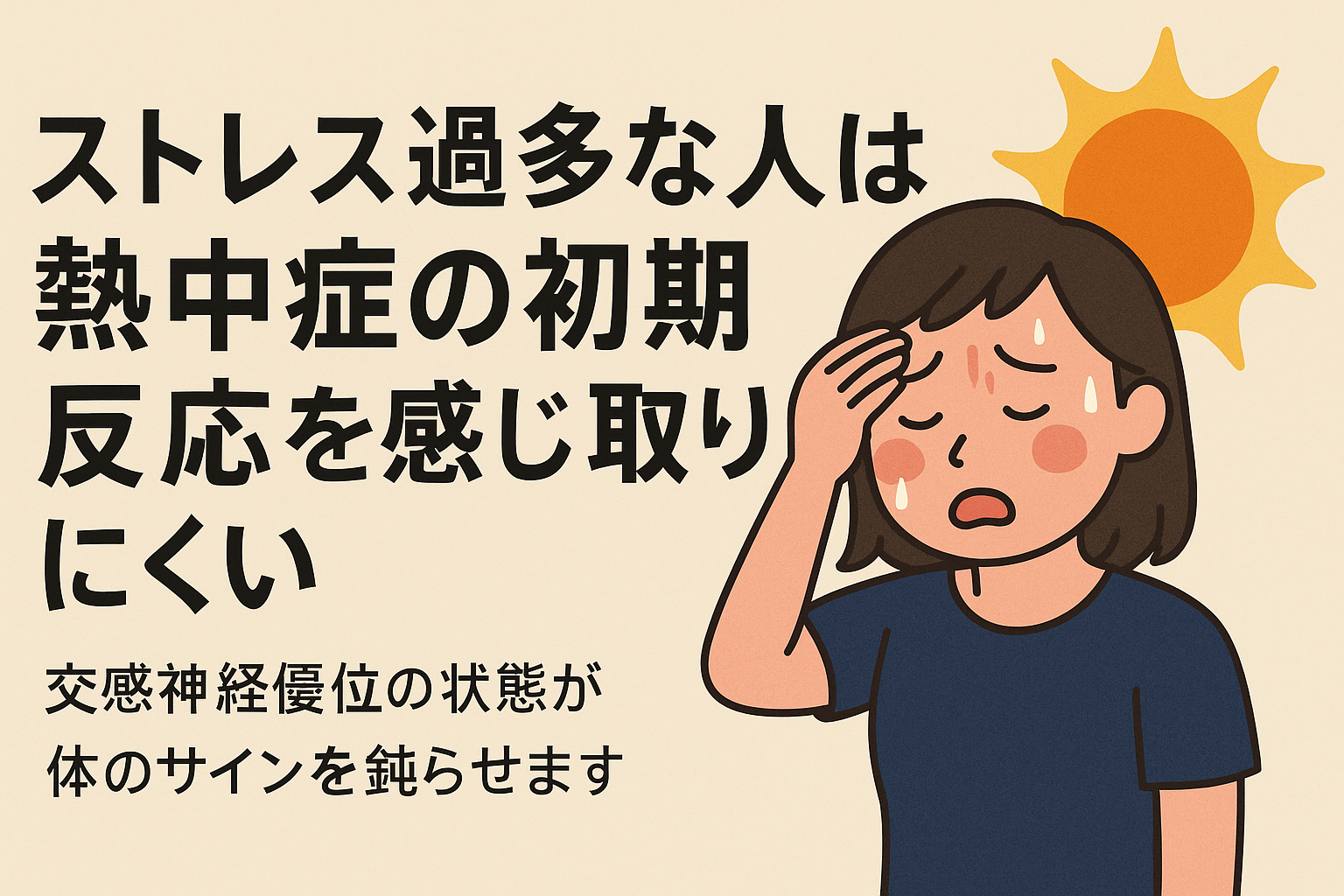
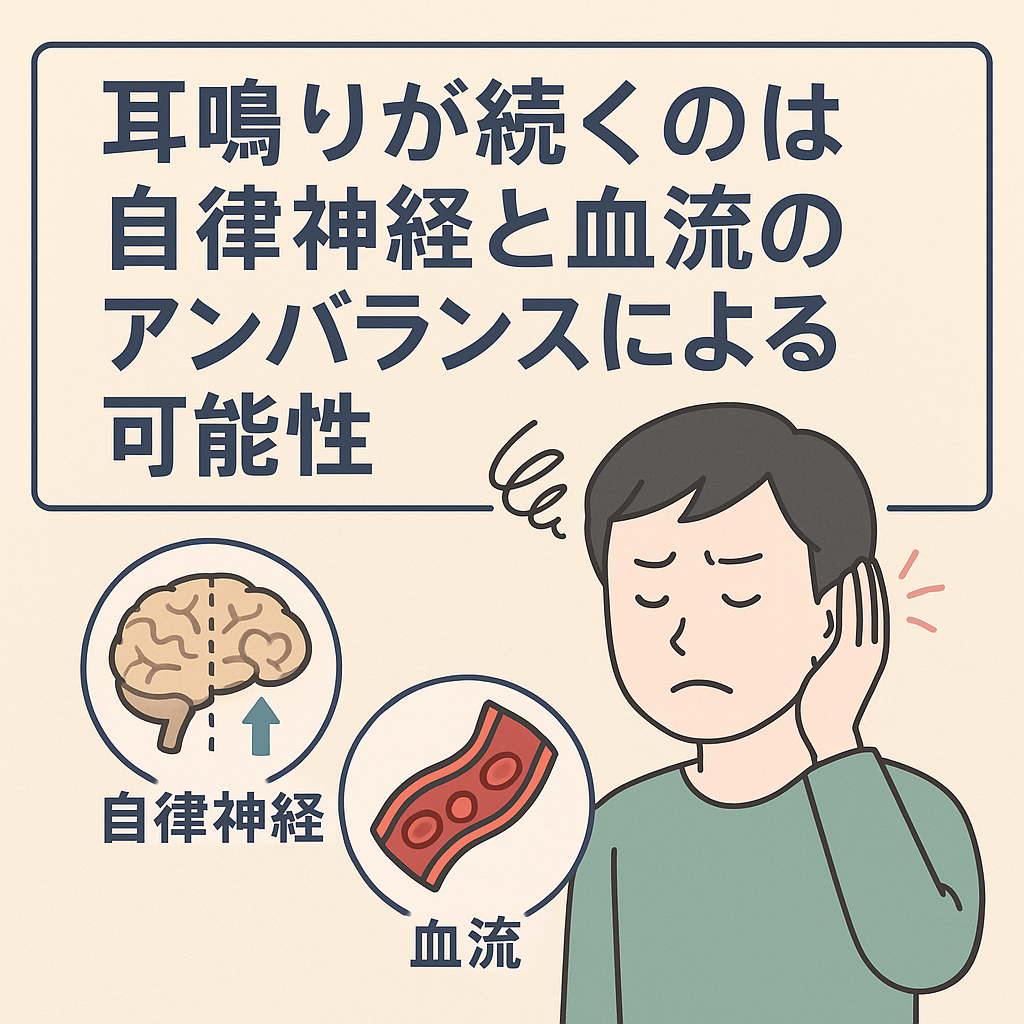

コメント