〜熱がこもると心肺に強い負担がかかります〜
はじめに
夏の暑さや湿度の高い日、または体調が優れないときに「急に動悸がして息苦しくなった」という経験はありませんか。
これは単なる暑さ負けや一時的な体力低下ではなく、深部体温の上昇によって心肺に大きな負担がかかっているサインかもしれません。深部体温とは、体の中心部(脳・心臓・内臓など)の温度であり、体表温とは異なります。深部体温が上がると、心拍数が増え、呼吸も浅く早くなり、心臓や肺が休む暇を失ってしまいます。
さらに、この状態は自律神経にも大きな影響を与えます。交感神経が過剰に働き続け、休息モードに入れなくなることで、心臓や肺の負担が長時間続き、体力低下や熱中症リスクを高めます。
今回は、動悸・息苦しさと深部体温の関係、自律神経・東洋医学的な視点からの原因と改善方法、そして当院での具体的な施術提案まで詳しく解説します。
1. 深部体温の上昇がもたらす心肺への負担
深部体温は通常、約37.0〜37.5℃の範囲で安定しています。しかし猛暑や湿度の高さ、室内環境の悪化、長時間の運動などで放熱が追いつかなくなると、深部体温は38℃以上に上昇します。
このとき、体は熱を逃がそうと皮膚血管を拡張し、心臓から全身へ大量の血液を送り出します。その結果、心拍数は急激に上がり(動悸)、酸素を運ぶために呼吸数も増え(息苦しさ)、体はフル稼働の状態になります。
特に注意が必要な状況
- 暑い屋外から涼しい室内へ急に移動した直後
- 室内でも風通しが悪く、湿度が高い環境
- 睡眠不足や体調不良時の軽い運動後
- 冷房の効いた部屋で長時間過ごした後の外出
2. 自律神経からみた動悸・息苦しさのメカニズム
自律神経は交感神経と副交感神経の2つから成り、体温や心拍、呼吸などを無意識に調節しています。
- 交感神経:活動モード、心拍数増加、血圧上昇、筋肉緊張
- 副交感神経:休息モード、心拍数低下、血圧低下、呼吸安定
深部体温が上がると、脳は体温を下げるために交感神経を活性化させます。心拍数を上げ、呼吸を早くし、血流を皮膚表面へ集中させます。しかしこの状態が長引くと、
- 心臓への負担増加
- 呼吸筋の疲労
- 脳や内臓への血流不足
が起こり、動悸や息苦しさが慢性化します。
3. 東洋医学的な解説
東洋医学では、動悸や息苦しさは**「心(しん)」と「肺(はい)」の機能不調**に深く関わります。
心(しん)
心は血液を全身に巡らせるだけでなく、「神(しん)」=精神活動の安定を司ります。深部体温の上昇により心が熱を帯びると、
- 動悸
- 不安感
- 不眠
などが現れます。これを**「心火上炎(しんかじょうえん)」**と呼びます。
肺(はい)
肺は呼吸とともに気(エネルギー)を全身に巡らせる役割があります。熱や湿気により肺が弱ると、
- 呼吸が浅くなる
- 息苦しさ
- 胸の圧迫感
が出やすくなります。
さらに、夏場は**「湿熱(しつねつ)」**が体にこもりやすく、気血の流れを滞らせます。この滞りが心肺への負担を増やし、動悸・息苦しさを悪化させます。
4. 当院での施術アプローチ
骨盤矯正
骨盤の歪みは体幹のバランスを崩し、横隔膜の動きを妨げます。骨盤を整えることで呼吸効率が向上し、酸素供給と放熱機能が改善します。
猫背矯正
猫背は胸郭を圧迫し、肺の拡張を制限します。矯正により肋骨の可動域が広がり、深い呼吸が可能になります。
鍼灸施術
心包経・肺経・腎経などにアプローチし、
- 気血の巡り改善
- 心火の鎮静
- 自律神経の安定化
を促します。灸による温熱刺激は、体表と深部の温度調節機能を回復させます。
頭部施術
頭部マッサージや頭鍼で脳の血流を改善し、視床下部(体温中枢)や延髄(呼吸中枢)の働きを整えます。
5. 通院目安
- 急性期:週2回(症状の安定と体温調節機能の回復を優先)
- リハビリ期:週1回(呼吸・心拍・姿勢の安定)
- メンテナンス期:月2〜3回(再発予防と季節変化への対応)
6. まとめ
動悸や息苦しさは、単なる一時的な不調ではなく、深部体温上昇による心肺・自律神経の負担サインです。特に夏場や湿度の高い日は早めのケアが重要です。当院では骨格・筋肉・神経・東洋医学の4本柱から総合的にアプローチし、体温調節機能と呼吸・心拍の安定を目指します。
予約はLINE・ホームページで24時間受付中。気になる症状がある方は、早めの来院をおすすめします。


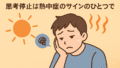

コメント