はじめに
「どれだけ寝ても眠い」「朝起きてもスッキリせず、午前中ずっとぼーっとしている」「昼寝をしても眠気が取れない」——そんな日々が続いていませんか?
季節の変わり目や気圧の変動が大きい時期、特に秋から冬へ移行するこの時期になると、こうした“眠っても眠い”という訴えをされる方が非常に多くなります。
睡眠時間は足りているのに、なぜこんなにも眠気が抜けないのか?
その背景には、「副交感神経」が過剰に働きすぎてしまっている可能性があります。副交感神経は本来「休息と回復」を司る大切な神経ですが、バランスが崩れて過剰反応を起こすと、体が“休むモード”から抜け出せず、活動スイッチが入らない状態になってしまうのです。
この記事では、眠っても眠い状態が続く原因を自律神経の仕組みから解説し、東洋医学の視点での体の状態、そして当院の骨盤矯正・猫背矯正・鍼灸・頭部施術がどのように改善へ導くかを詳しくご紹介します。
1. 自律神経のバランスが「眠気」を左右する
私たちの体は、「交感神経」と「副交感神経」という2つの自律神経がバランスを取り合いながら働くことで、昼と夜、活動と休息の切り替えを行っています。
- 交感神経…日中の活動モード。脳や筋肉へ血流を送り、集中力や判断力、体の動きを高めます。
- 副交感神経…夜や休息時のモード。消化吸収や修復・回復を促し、眠りへと導く働きがあります。
本来なら、朝日を浴びることで交感神経が優位になり、夜になると副交感神経が優位になるという自然なリズムが保たれています。しかし、自律神経の切り替えが乱れると、昼間でも副交感神経が優位なままになってしまい、「体がずっと休息モード」という状態に陥ります。
この状態では、脳の覚醒レベルが上がらず、どれだけ寝ても疲労が抜けず、日中の集中力も落ちてしまいます。まるで“常に眠気がまとわりついている”ような感覚になるのは、この自律神経の過剰な副交感神経反応が関係しているのです。
2. 副交感神経が過剰に働く主な原因
(1) 季節の変化・気圧変動による生体リズムの乱れ
秋から冬への移行期は、日照時間が短くなり、朝の光刺激が不足しやすくなります。光刺激は交感神経のスイッチを入れる大切な合図です。これが不足すると、朝になっても副交感神経が切り替わらず、“眠いまま一日が始まる”という状態になりがちです。
また、低気圧や寒暖差も自律神経の乱れを引き起こします。体は環境の変化に合わせて自律神経を調整しますが、その負担が大きくなると「副交感神経を優位にしてエネルギーを温存しよう」とする反応が強くなり、眠気が増してしまいます。
(2) 慢性疲労・ストレスによる反動
長期間、交感神経が優位な生活(過労・ストレス・緊張など)が続いた後、体は反動として副交感神経を強く働かせることがあります。これは「体を守る防御反応」でもありますが、過剰になると活動性が極端に低下し、眠気・倦怠感・無気力感が強まります。
(3) 背骨や姿勢の歪みによる神経伝達の不良
自律神経は背骨の内側を走る脊髄神経から枝分かれして全身に分布しています。背骨の歪みや猫背姿勢が続くと、この神経伝達が滞り、交感神経への切り替え信号が弱くなります。その結果、副交感神経がブレーキをかけ続けてしまい、体が「休息状態から抜け出せない」という状況に陥ります。
3. 東洋医学から見た「眠っても眠い」体の状態
東洋医学では、体が常に眠い状態を「気の巡りが滞り、陽気が昇らない状態」と捉えます。主な原因として以下が挙げられます。
◆ 脾(ひ)の機能低下:エネルギーを作れず気が足りない
脾は飲食物から気・血・水を作り出す臓腑です。脾の働きが弱ると、十分な気が生み出せず、全身を巡るエネルギーが不足します。その結果、体は常にだるく、眠気が取れない状態になります。
◆ 肝(かん)の疏泄不良:気が停滞して頭が冴えない
肝は気の流れをスムーズにする臓腑です。ストレスや自律神経の乱れで肝の働きが滞ると、気が上に昇らず、頭がぼんやりとし、眠ってもスッキリしません。
◆ 腎(じん)の精虚:生命力の低下で「陽」が湧かない
腎は生命力の源であり、活動の根本を担います。腎が弱ると、活動に必要な「陽気」が不足し、朝になっても体が目覚めず、休息状態が続いてしまいます。
東洋医学的な改善は、「気を補い、陽気を高め、気の流れを整える」こと。これができると、眠っても眠いという状態は自然と解消していきます。
4. くろちゃん鍼灸整体院での改善アプローチ
眠気が取れない原因は、単なる「寝不足」ではなく、体の根本的なバランスの乱れです。当院では、次の4つのアプローチを組み合わせて、副交感神経の過剰反応を整え、自然な活動リズムを取り戻すお手伝いをします。
① 骨盤矯正:自律神経の土台を整える
骨盤は背骨の土台であり、自律神経の中枢である脊髄神経の安定にも関わります。骨盤が前傾・後傾したり歪んでいると、脊椎の配列が乱れ、神経の伝達がスムーズに行われません。
骨盤矯正で重心と骨格のバランスを正すことで、交感神経・副交感神経の切り替えがしやすい環境をつくり、「朝スイッチが入る体」に整えていきます。
② 猫背矯正:胸郭を開き、覚醒信号を引き出す
猫背姿勢は胸郭を圧迫し、呼吸が浅くなります。呼吸の浅さは酸素供給の低下だけでなく、「覚醒ホルモン(オレキシン)」の分泌低下にもつながり、眠気を強めてしまいます。
猫背矯正で姿勢を整え、深い呼吸ができるようになると、自律神経の切り替えがスムーズになり、朝から頭がスッキリと働くようになります。
③ 鍼灸施術:副交感神経の過剰反応を沈める
鍼灸は自律神経の調整に非常に効果的です。ツボ刺激によって脳の視床下部・自律神経中枢へ直接アプローチし、副交感神経の過剰な興奮を鎮め、バランスを整えることができます。
特に、脾・肝・腎の経絡を整えることで「気」を補い、「陽気」を引き上げることができるため、東洋医学的にも“活動スイッチ”を押す力になります。
④ 頭部施術:脳の覚醒レベルを引き上げる
頭皮や後頭下筋群への施術は、脳血流を促進し、覚醒中枢の働きを高めます。副交感神経が優位でぼんやりしている状態でも、脳がしっかりと「目覚める」環境を整えることができるため、朝のだるさや昼間の眠気が和らぎやすくなります。
5. 改善のための通院ペース
眠っても眠い状態は、長年かけて自律神経が乱れてきた結果であることが多く、1〜2回の施術で劇的に変わることは稀です。段階的な改善が大切です。
- 急性期(最初の2〜3週間):週2回の施術で自律神経のリズムを再構築
- リハビリ期(1〜1.5ヶ月):週1回で切り替えスイッチを安定させる
- メンテナンス期(2ヶ月目以降):月2〜3回で再発を防ぎ、快調な状態を維持
6. まとめ:眠気は「体からのSOS」です
「寝ても寝ても眠い」という状態は、ただの“疲れ”ではなく、「体が活動モードに戻れない」という自律神経の乱れからのサインです。
副交感神経の過剰反応は、現代社会のストレスや季節環境の影響で多くの方に起こっており、放置すると慢性疲労・うつ症状・自律神経失調症へ進行することもあります。
早めに体の声を受け止め、根本から整えることで、朝の目覚めが軽くなり、昼間の集中力やパフォーマンスも大きく変わってきます。
ご予約・お問い合わせ
くろちゃん鍼灸整体院では、
📍急性期は週2回、📍リハビリ期は週1回、📍メンテナンス期は月2〜3回の施術ペースで自律神経を整え、快適な毎日へ導きます。
🌙LINE・ホームページから24時間予約受付中!
施術者が1人のため、予約が取りづらくなっております。お早めにご連絡ください!
✅ LINE・ホームページから24時間予約受付中
今すぐご予約はこちらから!相談も予約もLINEでのご連絡が便利です!
📱LINE![]()




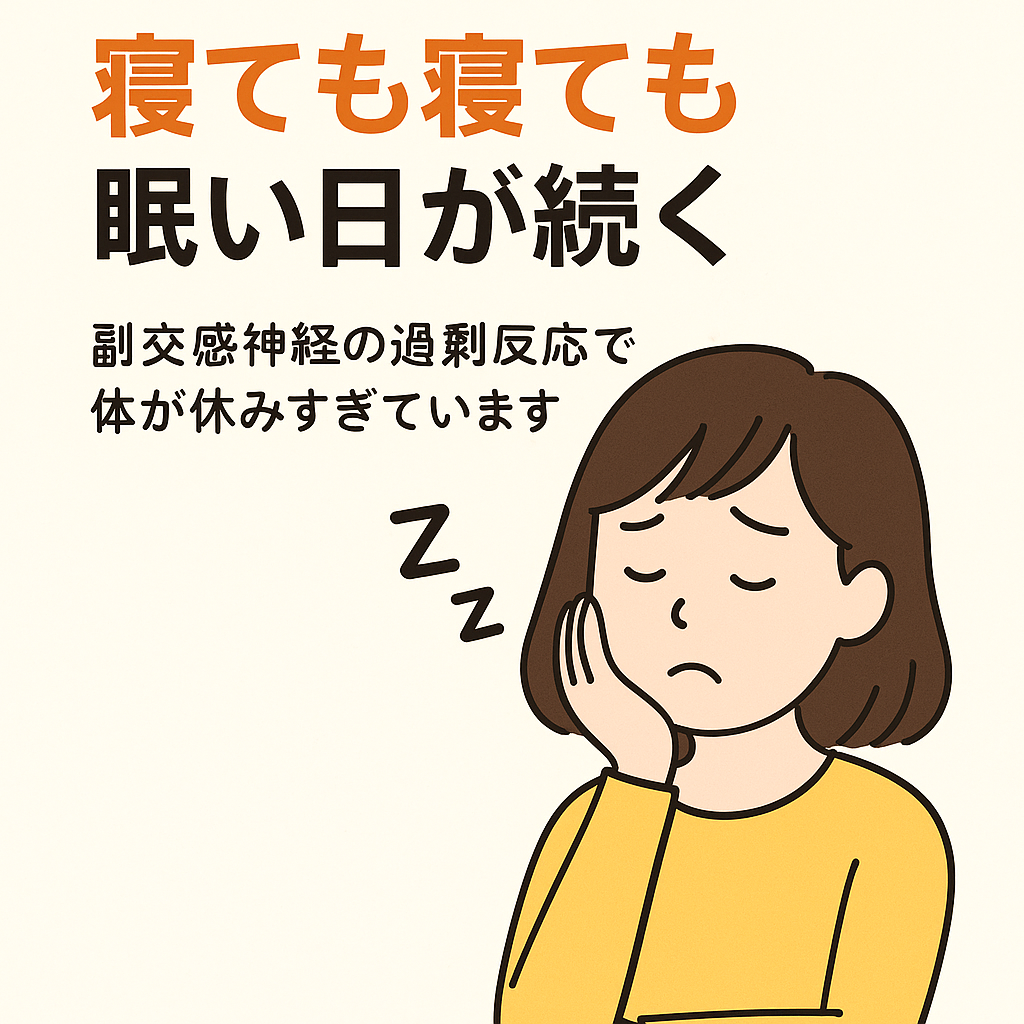
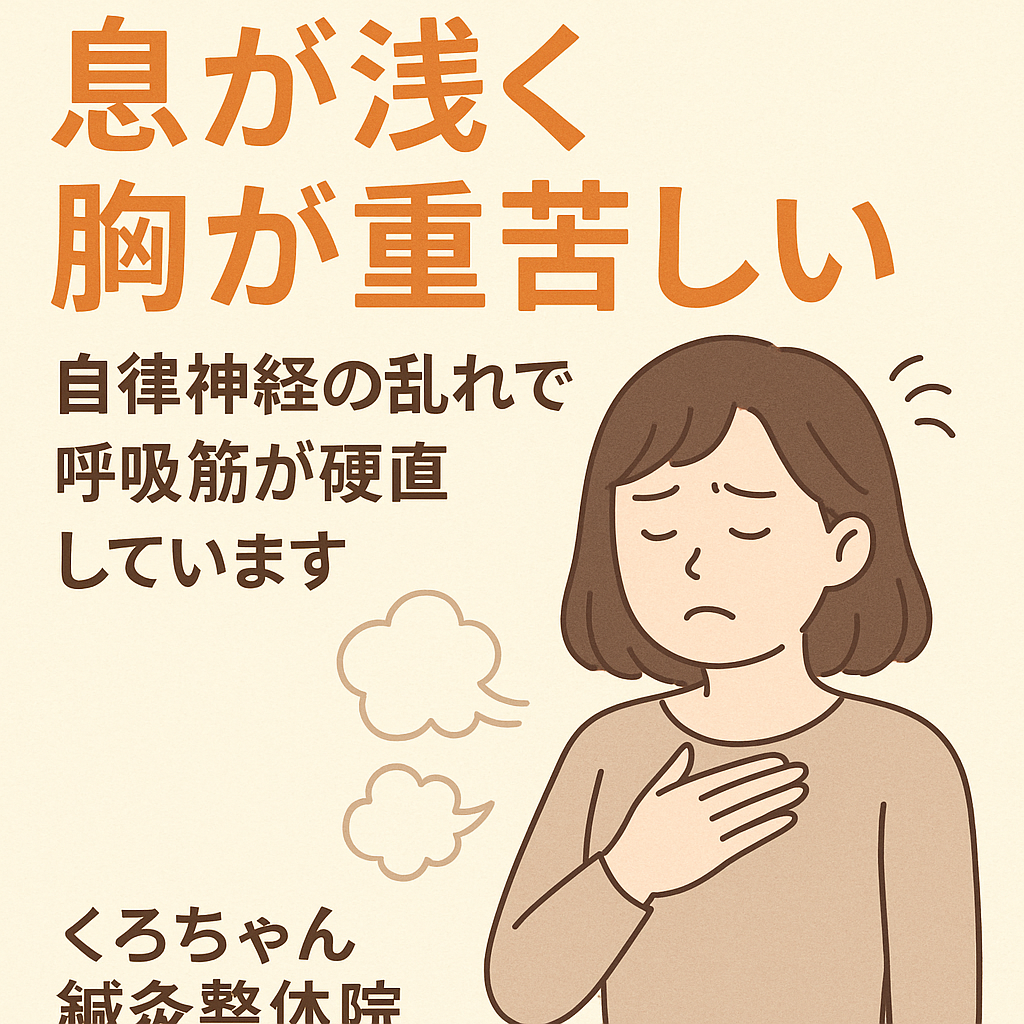

コメント