〜熱中症の夜間型や睡眠中の脱水の可能性も〜
はじめに
朝目覚めた瞬間から体が重い、頭がぼんやりする、起き上がるのに時間がかかる——そんな経験はありませんか?
「寝起きが悪い」の原因は単なる寝不足や疲労だけではありません。夏場や湿度が高い時期には、夜間の体温調節がうまくいっていないことが背景にあるケースが増えています。
特に近年は、夜間でも室温が下がらない熱帯夜やエアコンの使い方の誤りで、熱中症の夜間型や睡眠中の脱水が起こりやすくなっています。これは自律神経の働きに深く関係しており、東洋医学的にも「陰陽の切り替え」や「津液(体液)の不足」といった状態で説明できます。
本記事では、西洋医学と東洋医学の両面から夜間の体温調節不良の原因を解説し、くろちゃん鍼灸整体院で行っている骨盤矯正・猫背矯正・鍼灸施術・頭部施術による改善方法まで詳しくお伝えします。
1. 夜間の体温調節が乱れるメカニズム(西洋医学編)
1-1. 自律神経と体温コントロール
体温は自律神経が24時間体制で管理しています。日中は交感神経優位で代謝を高め、体温をやや高めに保ちます。夜間は副交感神経が優位となり、体温を下げて深い眠りを促します。この「体温の夜間低下」が睡眠の質を決める重要なポイントです。
しかし、室温や湿度が高いと体温を下げにくくなり、汗をかいても蒸発せず熱がこもります。その結果、副交感神経に切り替わりにくく、眠りが浅くなるのです。
1-2. 熱中症の夜間型
日中だけでなく、夜間に起こる熱中症があります。
寝ている間に体温が下がらず、汗で体液が失われ続けると、体内の水分・ミネラル不足と高体温状態が同時進行します。これが夜間型熱中症です。特に高齢者やエアコンを使わない習慣のある人に多く見られます。
1-3. 睡眠中の脱水
睡眠中も呼吸や発汗で水分は失われています。夏場はコップ1〜2杯分の水分が体から抜けると言われています。脱水が進むと血流が滞り、脳や筋肉への酸素供給が減り、翌朝のだるさや頭痛の原因になります。
2. 東洋医学からみた夜間の体温調節不良
2-1. 陰陽の切り替え不全
東洋医学では、昼は「陽」、夜は「陰」が優位になると考えます。陽から陰への切り替えがうまくいかないと、夜になっても体が興奮状態(陽過多)になり、深い眠りに入れません。これは「心火亢盛(しんかこうせい)」や「肝陽上亢(かんようじょうこう)」として説明されます。
2-2. 津液不足と体温コントロール
汗や呼吸で失われる体液は「津液」と呼ばれ、体温調節にも不可欠です。津液が不足すると汗が出にくくなり、熱が体内にこもりやすくなります。これは「陰虚(いんきょ)」の状態に相当します。
2-3. 臓腑別の関係
- 心(しん):体温と精神状態を調整。心火が旺盛だと寝つきが悪い。
- 脾(ひ):水分代謝を担い、湿気の影響を受けやすい。
- 腎(じん):陰陽の根本。腎陰不足は夜間のほてりや寝汗を引き起こす。
3. くろちゃん鍼灸整体院での改善アプローチ
3-1. 骨盤矯正
骨盤の歪みは自律神経の中枢である腰椎周辺の神経伝達を妨げます。骨盤を正しい位置に戻すことで、血流と神経の働きが改善し、夜間の体温調節がスムーズになります。
3-2. 猫背矯正
猫背は胸郭の動きを制限し、呼吸が浅くなります。深い呼吸は副交感神経の働きを促すため、胸を開く猫背矯正は眠りの質向上に直結します。
3-3. 鍼灸施術
東洋医学の理論に基づき、「百会」「安眠」「風池」などのツボを刺激し、自律神経を整えます。さらに、経絡に沿って熱のこもりを解消し、陰陽のバランスを調整します。
3-4. 頭部施術
頭皮や後頭部の緊張を緩めることで脳血流が改善。脳の温度調節中枢(視床下部)の働きを高め、夜間の体温コントロールを助けます。
4. 通院の目安
- 急性期(強い不調時):週2回
- リハビリ期(改善途中):週1回
- メンテナンス期(再発予防):月2〜3回
5. 予約方法
くろちゃん鍼灸整体院では、LINE・ホームページから24時間予約受付中。お仕事や家事の合間にも簡単に予約できます。
✅ LINE・ホームページから24時間予約受付中
今すぐご予約はこちらから!相談も予約もLINEでのご連絡が便利です!
📱LINE![]()




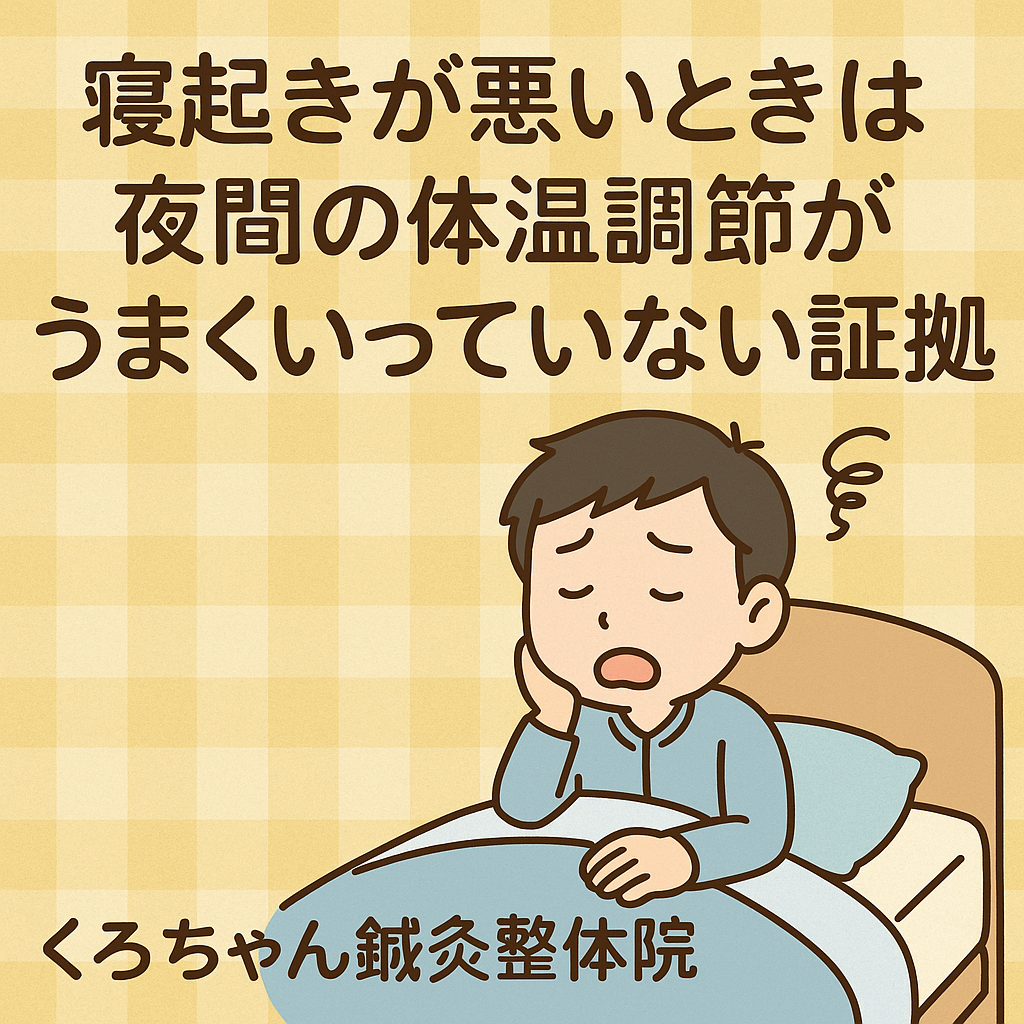


コメント