〜気圧の変化と暑さが自律神経の負担を増やす〜
はじめに
梅雨が明けると、一気に真夏の強い日差しと蒸し暑さが押し寄せます。
この時期、「体がだるい」「頭痛が続く」「食欲が出ない」「寝ても疲れが取れない」といった不調を訴える方が増えます。
原因は単なる暑さだけでなく、梅雨明け特有の気圧変化と急激な気温上昇が、自律神経に大きな負担を与えることにあります。
さらに、体温調節がうまくいかない状態で猛暑にさらされると、熱中症のリスクも急上昇します。
つまり、梅雨明けの不調を乗り越えるには、**熱中症対策と自律神経ケアを同時に行う「Wケア」**が欠かせません。
本記事では、西洋医学と東洋医学の両面からこの季節の体調不良を解説し、当院で行っている骨盤矯正・猫背矯正・鍼灸施術・頭部施術による効果的なケア方法をご紹介します。
梅雨明けに体調を崩しやすい理由
気圧変化による自律神経への負担
梅雨が終わる直前から明けた直後にかけて、天気は急変しやすく、気圧の上下動も激しくなります。
自律神経は気圧の変化を感じ取り、血管の収縮や拡張、心拍数、発汗などを調整しますが、急激な変化が繰り返されると交感神経と副交感神経の切り替えがスムーズに行えなくなります。
その結果、頭痛・めまい・倦怠感・集中力低下といった症状が現れやすくなります。
気温と湿度の急上昇
梅雨明け後は最高気温が30℃を超え、湿度も高くなります。
体温は汗をかくことで下げられますが、高湿度では汗が蒸発しにくく、放熱が妨げられます。
この状態で外出や作業を続けると、体内の熱がこもりやすくなり、熱中症へと進行する危険性が高まります。
東洋医学から見た梅雨明けの体調不良
東洋医学では、梅雨時は「湿邪」が体内に停滞しやすく、消化器系(脾胃)や循環系の働きを弱めると考えます。
湿邪は重く停滞する性質を持ち、だるさ・むくみ・食欲不振などを引き起こします。
梅雨が明けて気温が急上昇すると、この湿邪に「暑邪」が加わり、湿熱という状態になります。
湿熱は体内の熱と水分代謝を乱し、熱中症のリスクを高めます。
自律神経と熱中症の関係
自律神経は体温調節の中枢でもあり、発汗や血流コントロールを担っています。
しかし、気圧変化や高温多湿環境で過剰に働かされると、次のような悪循環が起こります。
- 気圧変化で交感神経が緊張し、血管収縮・筋肉緊張が増す
- 発汗や放熱がうまくいかず、体温が上昇
- 体温上昇でさらに交感神経が優位になり、心拍数が上昇
- 脱水や電解質不足が加わり、熱中症の危険が高まる
つまり、梅雨明けの時期は「自律神経が疲れて体温調節できない状態」で猛暑を迎えることが多く、熱中症予防のためには自律神経の安定化が不可欠です。
当院でのWケア施術
骨盤矯正
骨盤は全身のバランスの土台です。骨盤が歪むと血液・リンパの流れが滞り、熱が体内にこもりやすくなります。
梅雨明けのだるさやむくみは、骨盤矯正で下半身の循環を改善することで軽減されます。
猫背矯正
猫背は胸郭を圧迫し、呼吸が浅くなります。呼吸が浅いと酸素が不足し、放熱効率も低下します。
猫背矯正により胸を開き、深い呼吸を促すことで、自律神経の安定化と熱放散能力の向上が期待できます。
鍼灸施術
東洋医学では、湿邪・暑邪による不調に対して「脾胃の強化」「気の巡り改善」「熱の排出」を目的に鍼灸を行います。
例えば、足三里・陰陵泉・合谷・百会などのツボを用い、消化機能を高め、頭部の熱を逃がす施術を行います。
これにより、自律神経の働きが整い、体温調節機能が回復します。
頭部施術
頭部には自律神経の中枢である視床下部や脳幹とつながるポイントがあります。
軽い圧や刺激で血流を改善し、脳の温度を下げる効果が期待できます。
頭痛・頭重感・集中力低下がある方に特に有効です。
通院の目安
- 急性期(強いだるさ・頭痛・めまいが続く時期):週2回
- リハビリ期(症状が落ち着き始めた時期):週1回
- メンテナンス期(予防・季節の変わり目ケア):月2〜3回
予約方法
当院は LINE予約・ホームページ予約にて24時間受付 しております。
体調の変化を感じたら、早めのケアが回復の近道です。
✅ LINE・ホームページから24時間予約受付中
今すぐご予約はこちらから!相談も予約もLINEでのご連絡が便利です!
📱LINE![]()





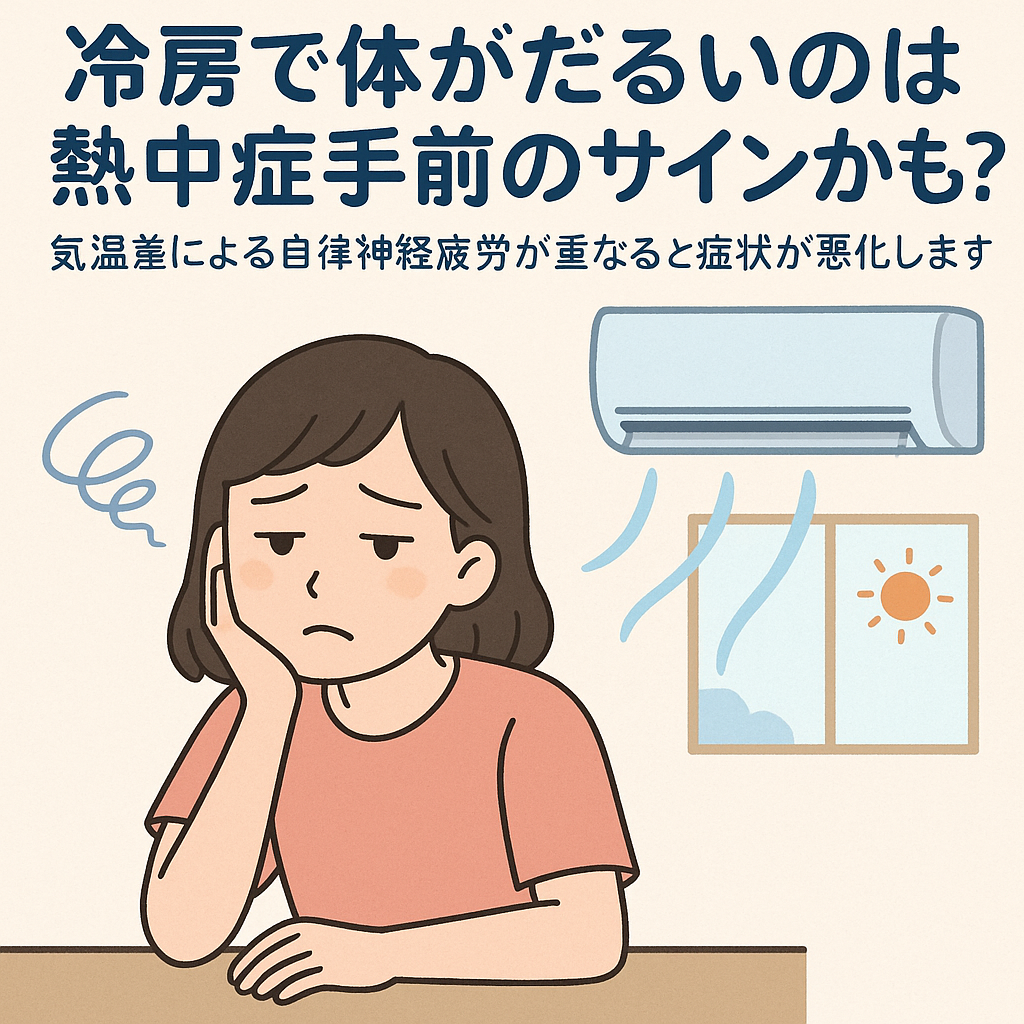

コメント