はじめに
「昨日まで平気だったのに、今朝からお腹が痛い…」「寒くなってから、食後にお腹がゴロゴロしてトイレに駆け込むことが増えた」
そんな経験はありませんか?
秋から冬へと向かうこの時期、朝晩の冷え込みが一気に強くなると、お腹の不調が出やすくなる方がとても多いです。
特に、日中との寒暖差が大きい日は、体がその変化に追いつけず、自律神経や内臓の働きが乱れやすくなります。
「冷え」というのはただの温度の問題ではなく、体の内部環境や神経のバランスに深く関わる重要なサイン。
そしてその背景には、自律神経の働きと、東洋医学が長年大切にしてきた「冷えと脾胃(ひい)」の関係があります。
この記事では、そんな季節特有の腹痛の原因と、くろちゃん鍼灸整体院で行っている施術の効果を、現代医学と東洋医学の両面から詳しく解説していきます。
1. 急な冷えが体に与える衝撃とは?
● 気温の急降下で「自律神経」がパニックになる
人間の体は本来、外の気温が多少変化しても体温を一定に保つ仕組みを持っています。
この調整を担っているのが「自律神経」であり、特に交感神経と副交感神経のスイッチ切り替えが鍵になります。
- 気温が高い → 血管を広げて熱を逃がす(副交感神経優位)
- 気温が低い → 血管を収縮させて熱を逃さない(交感神経優位)
しかし、朝晩の冷え込みが急に訪れると、この切り替えがスムーズにいかず、自律神経が過剰反応してしまうのです。
その結果、腸の動きが乱れたり、胃腸への血流が低下して消化が滞ったりして、腹痛が起きやすくなります。
● 「冷え」は内臓にとって大敵
お腹の中の臓器はとてもデリケートで、たった1〜2℃の温度変化でも機能が低下します。
特に腸は冷えに弱く、腸の温度が下がると以下のような反応が起きやすくなります:
- 腸の蠕動運動(ぜんどう)が過剰になり、下痢や腹痛が起こる
- 蠕動が弱まってガスがたまり、膨満感や鈍痛が出る
- 腸内環境が悪化して免疫力が低下する
つまり、冷え=体の中心部が弱るということ。これが秋冬に多い腹痛の本質です。
2. 東洋医学で見る「冷え」と腹痛の関係
東洋医学では、「冷え」は単なる温度の問題ではなく、体の気(エネルギー)や血(血流)の巡りが滞っている状態と捉えます。
特に腹痛との関係が深いのが「脾(ひ)」と「胃(い)」です。
● 「脾胃虚寒(ひいきょかん)」:冷えによって脾胃が弱る
東洋医学でよく使われる言葉に「脾胃虚寒(ひいきょかん)」という病証があります。
これは、消化吸収を担う脾と胃が冷えによって弱り、腹痛や下痢が起きる状態を指します。
特徴的な症状としては:
- 食後にお腹が痛くなる
- 温かい飲み物で少し楽になる
- 下腹部が冷えていて触ると冷たい
- 元気が出ず、だるい
- 手足も冷えやすい
これはまさに、「冷えが体の中心に入り込んだ」サインです。
● 「寒邪(かんじゃ)」が体の中に侵入する
東洋医学では外から侵入する有害な気を「邪気(じゃき)」と呼びます。
その中でも**冷たい性質を持つ「寒邪(かんじゃ)」**は、筋肉を収縮させ、気血の流れを滞らせ、痛みを生じさせる性質があります。
寒邪が腹部に侵入すると、腸が硬くなり、気の巡りが滞って**「痛み・膨満感・冷え」**といった症状が現れます。
3. 自律神経と東洋医学の両面から見る腹痛のメカニズム
● 自律神経面のメカニズム
- 気温差ストレス → 交感神経が過剰 → 血管収縮
- 腸への血流が低下 → 消化機能が低下
- 副交感神経への切り替えが遅れる → 蠕動が乱れる → 腹痛
● 東洋医学面のメカニズム
- 寒邪が体表から侵入 → 腹部の陽気を損なう
- 脾胃の働きが低下 → 食物をうまく消化できない
- 気血の流れが滞る → 痛み・下痢・冷えが出る
両者は別の言葉で説明していますが、「冷えが腸の働きを乱す」という本質は同じです。
4. くろちゃん鍼灸整体院でのアプローチ
気温差で腹痛が起きる方は、「表面的な冷え対策(カイロ・腹巻など)」だけでは不十分です。
体の中から「冷えに負けない状態」に整えることが大切です。
くろちゃん鍼灸整体院では、自律神経と脾胃の両方にアプローチするために、以下の施術を組み合わせて行っています。
● 骨盤矯正:内臓の血流と位置を整える
骨盤が歪むと、腸や胃の位置がわずかにズレ、血流が滞りやすくなります。
骨盤矯正により骨盤内の血流を改善し、内臓の働きを高める環境を作ることで、冷えの影響を受けにくくなります。
特に腸は骨盤の中に収まっているため、骨盤のねじれや傾きがあると、冷えが入りやすく、腹痛も出やすくなります。
矯正で正しい位置に戻すことで、自律神経の反応も穏やかになり、腹部の温かさが持続しやすくなります。
● 猫背矯正:交感神経の緊張をゆるめる
猫背になると、交感神経が過剰になりやすく、自律神経の切り替えが滞ります。
猫背矯正で背骨のラインを整えることで、副交感神経が働きやすい姿勢になり、腸の動きが整ってきます。
特に「季節の変わり目で腹痛が出やすい人」は、背中が緊張していることが多く、姿勢の改善が腹部症状の軽減に大きく役立ちます。
● 鍼灸施術:脾胃の陽気を高め、冷えを追い出す
鍼灸は、冷えによって滞った「気血」を流し、脾胃の働きを高める効果があります。
腹部・背部・足のツボを使いながら、体の中心から温めることで、内臓の動きを活発にし、腹痛・下痢・膨満感を根本から改善していきます。
特に「関元(かんげん)」「中脘(ちゅうかん)」「足三里(あしさんり)」などのツボは、冷え腹に非常に効果的です。
● 頭部施術:自律神経の切り替えスイッチを入れる
脳は自律神経の司令塔です。頭部の緊張が強いと交感神経が優位になり、腸が過敏になります。
頭部へのアプローチによって脳の興奮を鎮め、副交感神経の働きを高めることで、腹部の症状が自然と落ち着いていきます。
5. 通院の目安とケアの流れ
- 急性期(症状が強い時期):週2回
- リハビリ期(体質の安定期):週1回
- メンテナンス期(再発予防):月2〜3回
腹痛は「治ったように見えても、冷えの根が残っている」ことが多いです。
しっかりケアしておくことで、次の季節の変化にも対応できる「ブレない内臓環境」をつくることができます。
6. まとめ ― 冷え腹は「体が出すSOS」
気温の急降下による腹痛は、単なる「お腹の冷え」ではなく、体が冷えストレスに対応できていないサインです。
自律神経と脾胃の働きを整えることで、季節の変化に強い体を手に入れることができます。
「毎年この時期になると腹痛が出る」「トイレが近くなる」
そんな方は、早めのケアが何より大切です。放っておくと慢性化してしまい、冬本番に体調を崩しやすくなります。
✅ 予約・お問い合わせ
くろちゃん鍼灸整体院では、
📍急性期は週2回/リハビリ期は週1回/メンテナンスは月2〜3回のペースで体質改善をおすすめしています。
LINE・ホームページから24時間予約受付中です。
施術者が一人のため、ご予約が取りづらくなっております。お早めにご連絡ください!
✅ LINE・ホームページから24時間予約受付中
今すぐご予約はこちらから!相談も予約もLINEでのご連絡が便利です!
📱LINE![]()






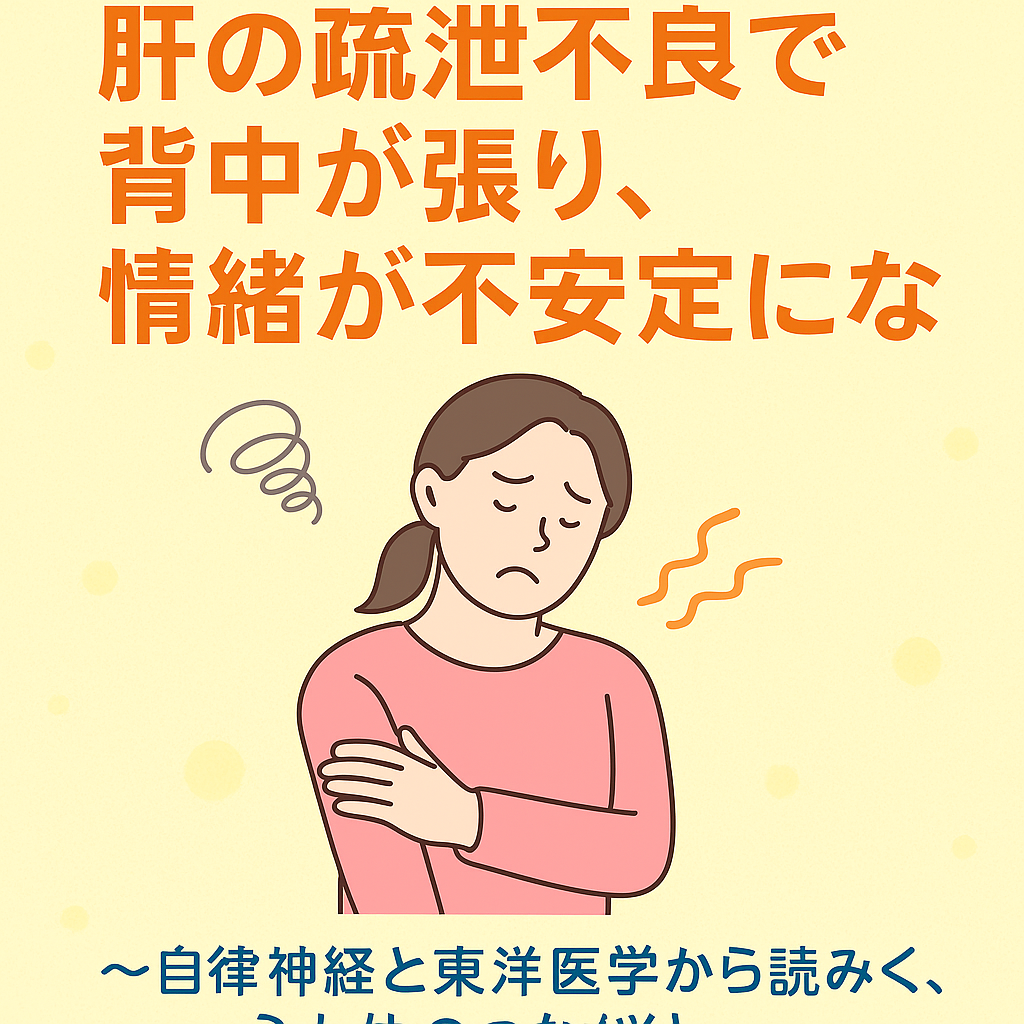
コメント