唇がカサつき、リップクリームを何度塗っても追いつかない——そんな症状の背景には、東洋医学でいう「肺燥(はいそう)」が隠れているかもしれません。単なる乾燥ではなく、体内の「潤い不足」が引き起こす不調として、東洋医学では重視される症候のひとつです。
肺と唇の関係 〜東洋医学からみた肺燥とは〜
東洋医学では、「肺は皮毛を主る(ひもうをつかさどる)」とされ、皮膚・毛髪・口唇などの外表に潤いを与える働きを担っています。肺が潤いを失うと、「肺燥」と呼ばれる状態になり、以下のような症状が現れます。
- 唇が乾燥してひび割れる
- のどの渇き、空咳、声枯れ
- 皮膚のカサつき
- 鼻の乾燥・出血
- 便秘気味
この「肺燥」は、秋の乾燥した気候、長時間の空調、過労、睡眠不足、辛い食事の摂りすぎなどがきっかけで悪化することがあります。
とくに唇の乾燥は、皮膚や口腔粘膜の潤いを調節する肺の働きが弱くなっているサインのひとつ。唇の状態は身体全体の「潤いバランス」を反映しているのです。
くろちゃん鍼灸整体院での改善アプローチ
当院では、肺燥による唇の乾燥に対して、身体全体の潤いを取り戻す施術を行っています。東洋医学の理論に基づいた以下の施術法が効果的です。
✅ 骨盤矯正:内臓機能と気血の巡りを整える
骨盤の歪みがあると、全身の気血の巡りが悪くなり、肺にも十分な栄養や水分が届けられません。骨盤矯正で土台を整えることで、呼吸器系へのエネルギー供給がスムーズになります。
✅ 猫背矯正:肺の可動域と酸素交換の質を改善
猫背によって胸郭が圧迫されると、肺の働きが制限されてしまいます。猫背矯正により胸が開くことで、呼吸が深くなり、潤いの供給も促進されます。
✅ 鍼灸施術:肺経・任脈・陰虚に関わる経穴を重点刺激
- 太淵(たいえん):肺経の原穴。肺の気を補い、乾燥を改善。
- 列缺(れっけつ):肺の経絡を通じ、潤いを補う経穴。
- 陰陵泉(いんりょうせん):水分代謝を高め、体内の潤いを保つ。
- 中脘(ちゅうかん)・天突(てんとつ):乾燥による咳や喉の渇きに有効。
これらのツボを用い、身体の内側から「潤す力」を引き出します。
✅ 頭部施術:自律神経調整で潤いの生産力を高める
乾燥にはストレスや睡眠の質も関係しています。頭部への施術で自律神経を整えることで、ホルモンバランスや体内水分の保持機能が安定し、唇や粘膜の状態が改善されます。
施術ペースと来院の目安
- 急性期:週2回
- リハビリ期:週1回
- メンテナンス期:月2〜3回
症状の強い時期は短期集中での調整を行い、改善後も季節の変わり目や乾燥しやすい時期には定期的なケアがおすすめです。
ご予約はLINEまたはホームページから24時間受付中!
あなたの「潤い不足」を、東洋医学の力でサポートいたします。唇の乾燥が続く、のどの渇きが気になるなどのお悩みは、お気軽にご相談ください。
✅ LINE・ホームページから24時間予約受付中
今すぐご予約はこちらから!相談も予約もLINEでのご連絡が便利です!
📱LINE![]()





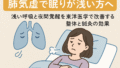

コメント