東洋医学の説明(脾胃不和について)
脾胃不和とは、東洋医学で言う「脾」と「胃」の働きが正常に調和していない状態を指します。脾は消化・吸収を司り、胃は食物を受け入れて消化する役割を担います。これらの機能がうまく連携しないと、食後に膨満感や胃の張り感、消化不良が起こりやすくなります。
脾胃不和の原因としては、過食や食べ過ぎ、冷たい食べ物や飲み物の摂取、ストレスや不規則な生活習慣が挙げられます。特に、脾が弱いと食物をうまく消化・吸収できず、胃に負担をかけるため、膨満感や不快感が強くなります。また、精神的な疲れやストレスも脾胃の調和を崩す原因となります。
症状としては、
- 食後の膨満感
- 胃の張りや不快感
- 食欲の不振
- 消化不良感
- 体重増加や便秘など
これらの症状を放置すると、慢性的な消化不良や疲れが蓄積し、さらなる体調不良を引き起こす可能性があります。
改善のための施術提案
- 骨盤矯正
骨盤の歪みや姿勢の不良が脾胃の働きを阻害することがあります。骨盤矯正を行うことで、消化器系の機能が正常化し、内臓の圧迫を減らすことができます。これにより、食後の膨満感が軽減され、消化がスムーズになります。 - 猫背矯正
猫背によって内臓が圧迫され、消化機能が低下することがあります。正しい姿勢を維持することで、胃腸への圧力が減少し、膨満感を予防することができます。猫背矯正を通じて、内臓の働きを正常化しましょう。 - 鍼灸施術
鍼灸は、脾経や胃経に働きかけることで、消化機能の改善を促進します。特に「脾経」のツボに鍼を打つことで、脾の働きを強化し、消化不良や膨満感の軽減が期待できます。また、鍼灸は自律神経の調整にも効果があり、ストレスや精神的な負担を軽減します。 - 頭部施術
頭部のツボに刺激を与えることで、消化器系のバランスが整い、消化不良を改善します。ストレスや不安も頭部に影響を与えるため、リラックスできる環境を整えることで、消化機能が向上します。
通院頻度について
- 急性期: 週2回
- リハビリ期: 週1回
- メンテナンス: 月2〜3回
食後の膨満感が続く場合は、急性期に集中的に施術を受けることで症状の改善が見込めます。リハビリ期に入ると、週1回の施術で維持し、症状の再発防止が可能です。メンテナンス期では、月2〜3回の通院で健康を保ち続けることができます。
予約方法
- LINE: 24時間受付中
- ホームページ: 24時間受付中
どちらの方法でも簡単にご予約いただけますので、気軽にご連絡ください。
✅ LINE・ホームページから24時間予約受付中
今すぐご予約はこちらから!相談も予約もLINEでのご連絡が便利です!
📱LINE![]()



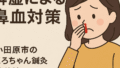

コメント