~東洋医学からのアプローチと整体・鍼灸による根本ケア~
なぜ夜だけ汗が出る?「腎陰虚」と寝汗の関係
東洋医学では、「陰」は体を潤し、冷ます役割を担っています。特に「腎陰」は生命の根本である“腎精”の一部であり、体内の水分・エネルギーをコントロールする重要な要素です。腎陰が不足すると、体内に抑えるべき“熱”がこもりやすくなり、就寝中に汗としてその熱を放出しようとすることで【寝汗】が出やすくなります。
東洋医学的な腎陰虚の特徴
- 午後〜夜間にかけてのほてり感
- 寝汗・盗汗(寝ている時だけの発汗)
- 口や喉の乾き
- 足腰のだるさ・無力感
- 耳鳴りや聴力の低下
- 不眠や途中覚醒
これらは、陰虚による「虚熱(体に必要な冷却力が足りず、内部に熱がこもる)」の表れです。腎陰は加齢や慢性疲労、過労、夜更かし、過度な発汗や発熱によって消耗しやすく、特に40代以降の女性に多く見られます。
骨盤矯正・猫背矯正で自律神経を整える
腎陰虚による寝汗は、自律神経の不安定さと密接に関わっています。特に「副交感神経がうまく働かず、交感神経が夜間に優位になる」ことで、体温調整が乱れ寝汗が出やすくなります。
当院のアプローチ
- 骨盤矯正により内臓の位置を安定させ、腎の働きをサポート
- 猫背矯正で肺・腎の経絡の流れを整え、自律神経を安定させます
- 姿勢改善による呼吸の質向上で「陰液」の消耗を減らします
鍼灸施術で腎陰を補い、熱を鎮める
東洋医学的な「腎陰虚」に対しては、補腎陰・清虚熱を目的とした鍼灸が効果的です。
使用する代表的な経穴
- 太渓(たいけい):腎陰を養う代表的なツボ
- 照海(しょうかい):腎経を潤す作用があり、寝汗に有効
- 復溜(ふくりゅう):腎気を引き締め、汗を止める働き
- 三陰交(さんいんこう):陰を養い、ホルモンバランスを整える
また、灸療法により陰陽のバランスを整え、虚熱を鎮める施術も組み合わせます。特に、腎経の熱を下げるように施灸することで、発汗が落ち着いていきます。
頭部施術で脳疲労を鎮め、夜間の過活動を抑制
寝汗が止まらない背景には、「日中の脳疲労やストレス」が関わることも少なくありません。頭部への鍼灸や手技によって脳の過活動を鎮め、自律神経の切り替えをスムーズにすることで、夜間の発汗症状が緩和されていきます。
通院の目安
- 急性期(症状が強い時期):週2回の施術で集中的に調整
- リハビリ期(症状が落ち着きはじめた時期):週1回の施術で安定を継続
- メンテナンス期(再発予防・体調管理):月2〜3回の施術で体質改善へ
ご予約方法
✅ LINE予約・ホームページより24時間受付中
初診の方もお気軽にご相談ください。
まとめ
「腎陰虚による寝汗」は、体の陰が消耗した状態からくる慢性症状です。ただの汗と思わず、東洋医学では“体のSOS”としてとらえるべきサインです。くろちゃん鍼灸整体院では、体質に合わせた施術を通じて、根本改善と再発予防をサポートいたします。
✅ LINE・ホームページから24時間予約受付中
今すぐご予約はこちらから!相談も予約もLINEでのご連絡が便利です!
📱LINE![]()






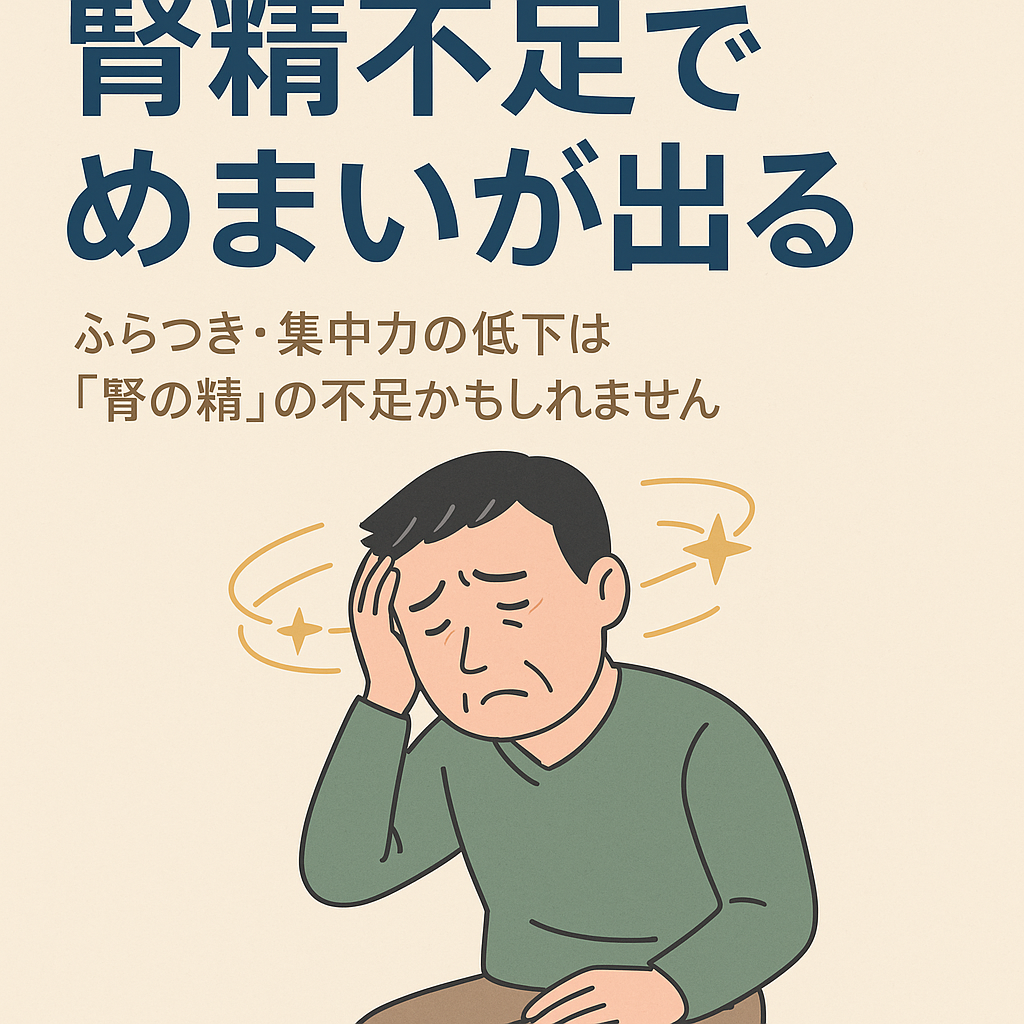
コメント