自律神経失調による発汗調整障害が関係します
はじめに
夏場や運動中、あるいは夜中に突然「足がつる」経験をしたことはありませんか?
一瞬で強い痛みに襲われ、動けなくなるあの感覚は、多くの方にとって馴染み深い症状です。しかし、この足のつりは単なる筋肉疲労だけが原因ではなく、熱中症による体温調節不良や、ミネラル不足、自律神経の乱れが複合的に関与している場合があります。
特に近年の猛暑では、室内でも熱中症リスクが高まり、発汗量が増えることでナトリウムやマグネシウム、カリウムなどのミネラルが失われやすくなります。さらに、自律神経が乱れると発汗や血流のコントロールが不安定になり、筋肉の異常収縮を引き起こしやすくなるのです。
本記事では、西洋医学と東洋医学の両面から「足がつりやすい人に潜む危険信号」について解説し、当院で行っている骨盤矯正・猫背矯正・鍼灸施術・頭部施術がどのように改善に役立つかを詳しくご紹介します。
1. 足がつりやすい原因とメカニズム(西洋医学的視点)
1-1 熱中症による発汗量増加と電解質喪失
汗には水分だけでなく、ナトリウム、カリウム、マグネシウム、カルシウムといったミネラルが含まれています。これらの電解質は、筋肉の収縮と弛緩をスムーズに行うために欠かせません。
発汗が過剰になるとこれらが体外に排出され、筋肉細胞内外の電解質バランスが崩れ、筋肉が過剰に収縮して「つる」状態になります。
1-2 脱水による血流不足
発汗で水分が失われると血液の粘度が高まり、筋肉への酸素・栄養供給が滞ります。この結果、乳酸などの代謝産物が蓄積しやすくなり、筋肉が痙攣を起こすリスクが上昇します。
1-3 自律神経失調による体温・発汗調整障害
交感神経と副交感神経のバランスが乱れると、汗腺の開閉や血管拡張・収縮の調整がうまくいかなくなります。特に交感神経が過剰に優位な状態では、常に身体が緊張モードとなり、筋肉の硬直や血流障害を引き起こしやすくなります。
2. 東洋医学からみた「足のつり」
東洋医学では、足のつりは**「気血不足」や「肝血虚」、または「湿熱」や「暑邪」**といった季節要因によって引き起こされると考えます。
- 気血不足:エネルギー(気)や栄養(血)が足りず、筋肉に十分な滋養が行き渡らない状態。慢性的な疲労や睡眠不足、加齢によって悪化。
- 肝血虚:肝は血を蔵し、筋を養う臓腑。肝血が不足すると筋肉の滋養が足りず、痙攣やつりを起こす。
- 湿熱:夏の高温多湿により体内に湿と熱がこもると、経絡の流れが阻害され、筋肉に異常反応が出やすくなる。
- 暑邪の影響:真夏の暑気(暑邪)が体に侵入し、体液を消耗させることで筋肉が乾き、収縮が強まる。
3. 当院の施術アプローチ
3-1 骨盤矯正
骨盤は下肢への血流・神経伝達の中継点です。歪みがあると下肢の血流が悪くなり、筋肉が酸素不足に陥りやすくなります。骨盤矯正により左右バランスを整えることで、足の筋肉がリラックスしやすい状態になります。
3-2 猫背矯正
猫背は胸郭の動きを制限し、呼吸が浅くなります。酸素供給が不足すると、末端筋肉の回復力も低下します。背骨のアライメントを整え、胸を開くことで、血流と酸素循環を改善します。
3-3 鍼灸施術
東洋医学的に「足のつり」に関連する経穴(承山・承筋・足三里など)や、全身の気血を整えるツボにアプローチします。これにより、筋肉の異常収縮を鎮め、再発防止にもつながります。
3-4 頭部施術
頭部の筋緊張や血流障害は、自律神経の働きに影響します。頭皮・後頭部の施術で脳血流を改善し、自律神経バランスを整えることで発汗調整能力を回復させます。
4. 通院の目安
- 急性期(症状が頻発する時期):週2回
- リハビリ期(症状が軽減してきた時期):週1回
- メンテナンス期(予防・体調維持):月2〜3回
5. まとめ
足がつりやすい人は、単なる筋肉疲労ではなく**「熱中症+ミネラル不足+自律神経の乱れ」**という複合型の要因が隠れている可能性があります。当院では、骨格・筋肉・神経・東洋医学の4方向からアプローチし、再発しにくい身体づくりをサポートします。
予約はLINE・ホームページで24時間受付中
✅ LINE・ホームページから24時間予約受付中
今すぐご予約はこちらから!相談も予約もLINEでのご連絡が便利です!
📱LINE![]()





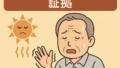
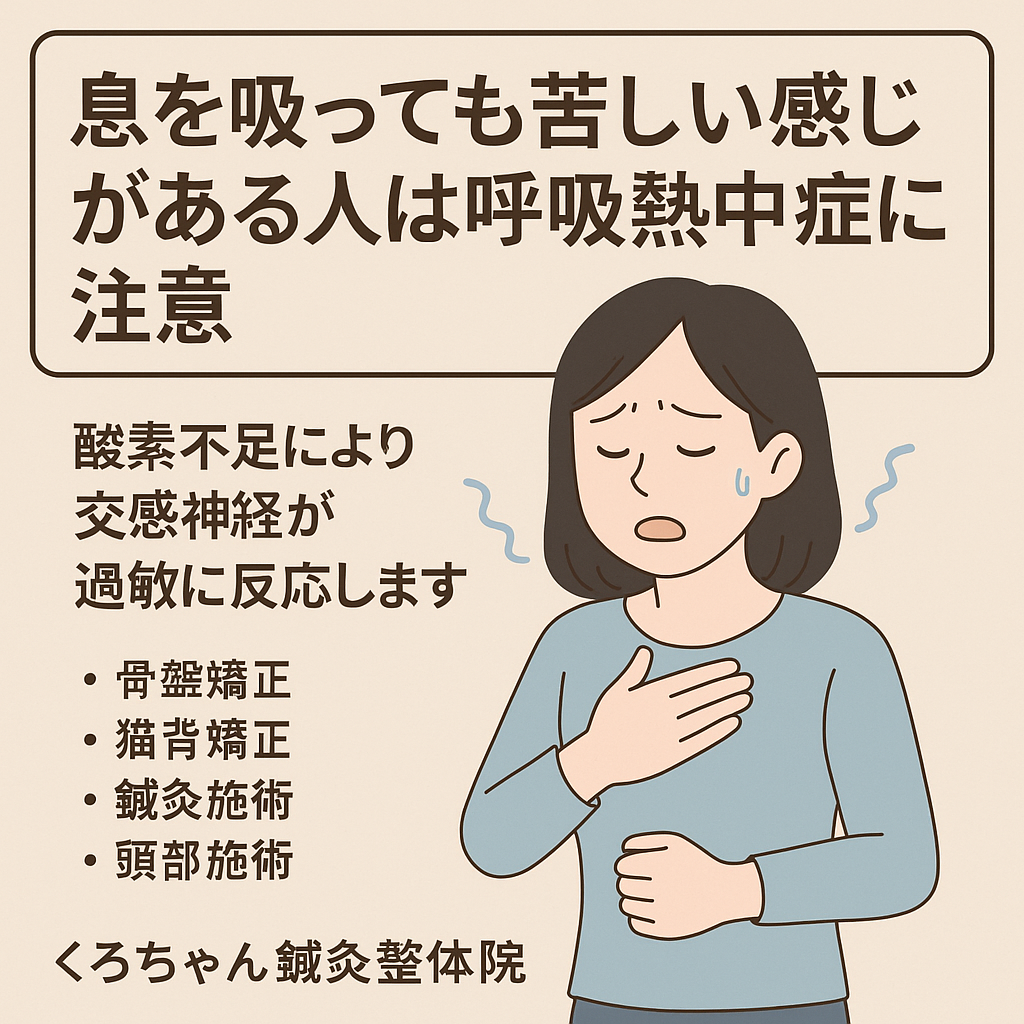
コメント