はじめに
最近、「呼吸が浅い」と感じる方が増えています。特にデスクワークやスマートフォン操作が長い人、ストレスを抱えている人に多く見られる特徴です。そして、そんな方が訴える症状のひとつが「頭痛」です。呼吸が浅くなると体内の酸素が不足し、脳や神経が過敏になって頭痛を引き起こすことがあります。本記事では、自律神経と東洋医学の観点から「呼吸の浅さと頭痛」の関係をわかりやすく解説し、くろちゃん鍼灸整体院での改善法をご紹介します。
呼吸が浅くなると何が起きるのか?
呼吸が浅いというのは、胸や肩ばかりで呼吸していて、横隔膜を使った深い呼吸(腹式呼吸)ができていない状態です。酸素を十分に取り込めないことで、次のような変化が起こります。
- 脳への酸素供給が減り、神経が過敏化
- 交感神経が過剰に働き、筋肉が緊張
- 血管が収縮し、血流が悪化
- 結果として「締め付けるような頭痛」や「重だるい頭痛」が出やすくなる
特にパソコンやスマホに集中していると、無意識に呼吸が止まりがち。これが長時間続くと、自律神経のバランスが崩れ、慢性的な頭痛の原因になります。
自律神経の乱れと頭痛の関係
自律神経は「交感神経」と「副交感神経」の2つのバランスで成り立っています。呼吸が浅いと交感神経が優位になり、常に体が緊張状態に。血管が収縮して脳への血流が滞り、頭痛を引き起こします。
逆に、副交感神経が優位になりすぎても、血管が過剰に拡張してズキズキするような偏頭痛を起こすことがあります。つまり、呼吸の乱れが自律神経のリズムを狂わせ、「頭痛を誘発するトリガー」になるのです。
東洋医学からみた「呼吸浅い人の頭痛」
東洋医学では、呼吸の浅い人は「気の巡り」が滞っていると考えます。特に「肝(かん)」と「肺(はい)」のバランスが乱れていることが多いです。
- 肝気鬱結(かんきうっけつ):ストレスや緊張で気の流れが滞り、頭に熱や圧がこもる
- 肺気虚(はいききょ):呼吸が浅く、酸素の巡り(気の巡り)が不足して頭が重くなる
また、肩や首まわりの筋肉が硬くなることで「気血」が頭にうまく届かず、酸素不足のようなだるい頭痛を感じることもあります。東洋医学では「気滞血瘀(きたいけつお)」という状態で、これが慢性頭痛の背景に多く見られます。
くろちゃん鍼灸整体院でのアプローチ
1. 骨盤矯正 ― 呼吸のリズムを全身で整える
呼吸の浅い方の多くは、骨盤の動きが固く、横隔膜の上下運動が制限されています。くろちゃん鍼灸整体院では、骨盤を中心に全身の歪みを整え、呼吸の深さを取り戻します。骨盤が安定すると、横隔膜が自然に動き出し、呼吸のリズムが深く整っていきます。
2. 猫背矯正 ― 胸郭の開きを改善
猫背は呼吸を浅くする最大の原因の一つ。胸が閉じていると肺が十分に膨らまず、肩や首の筋肉に負担がかかります。矯正によって胸郭を開くことで、自然と呼吸が深くなり、頭部への酸素供給が改善。これにより、頭痛の頻度や重さが軽減されます。
3. 鍼灸施術 ― 自律神経と気血の巡りを整える
鍼灸では「百会(ひゃくえ)」「風池(ふうち)」「合谷(ごうこく)」など頭痛と呼吸調整に関わる経穴(ツボ)を刺激します。これにより、自律神経のバランスを整え、脳への血流と酸素供給を改善。肩や首の緊張も和らぐため、頭痛の根本改善に繋がります。
4. 頭部施術 ― 酸素の流れを感じるリラックスケア
頭部を優しくほぐすことで、頭皮下の血流を改善し、脳の疲労感や重だるさを解消します。施術中に「スーッと頭が軽くなった」「息が深くなった」と感じる方も多く、酸素の流れを実感できます。
通院の目安
- 急性期:週2回(呼吸が浅く、頭痛が頻発している時期)
- リハビリ期:週1回(自律神経の安定を図る期間)
- メンテナンス期:月2〜3回(季節変化やストレス対策として)
呼吸の深さは一度整っても、ストレスや姿勢の崩れで再び浅くなることがあります。定期的なケアで自律神経を安定させましょう。
まとめ ― 呼吸を整えることが頭痛改善の第一歩
呼吸が浅い人の頭痛は、単なる筋肉のこりではなく、自律神経と酸素循環の問題が背景にあります。骨盤や姿勢を整え、呼吸の質を変えることで、体も心も軽くなります。
「頭が重い」「息苦しい」「集中できない」と感じたら、早めの施術がおすすめです。くろちゃん鍼灸整体院では、全身のリズムを整え、頭痛を根本から改善します。
📅 予約方法 LINE・ホームページで24時間予約受付中! 施術者が1人のため、予約が取りづらくなっております。お早めにご連絡ください。
✅ LINE・ホームページから24時間予約受付中
今すぐご予約はこちらから!相談も予約もLINEでのご連絡が便利です!
📱LINE![]()




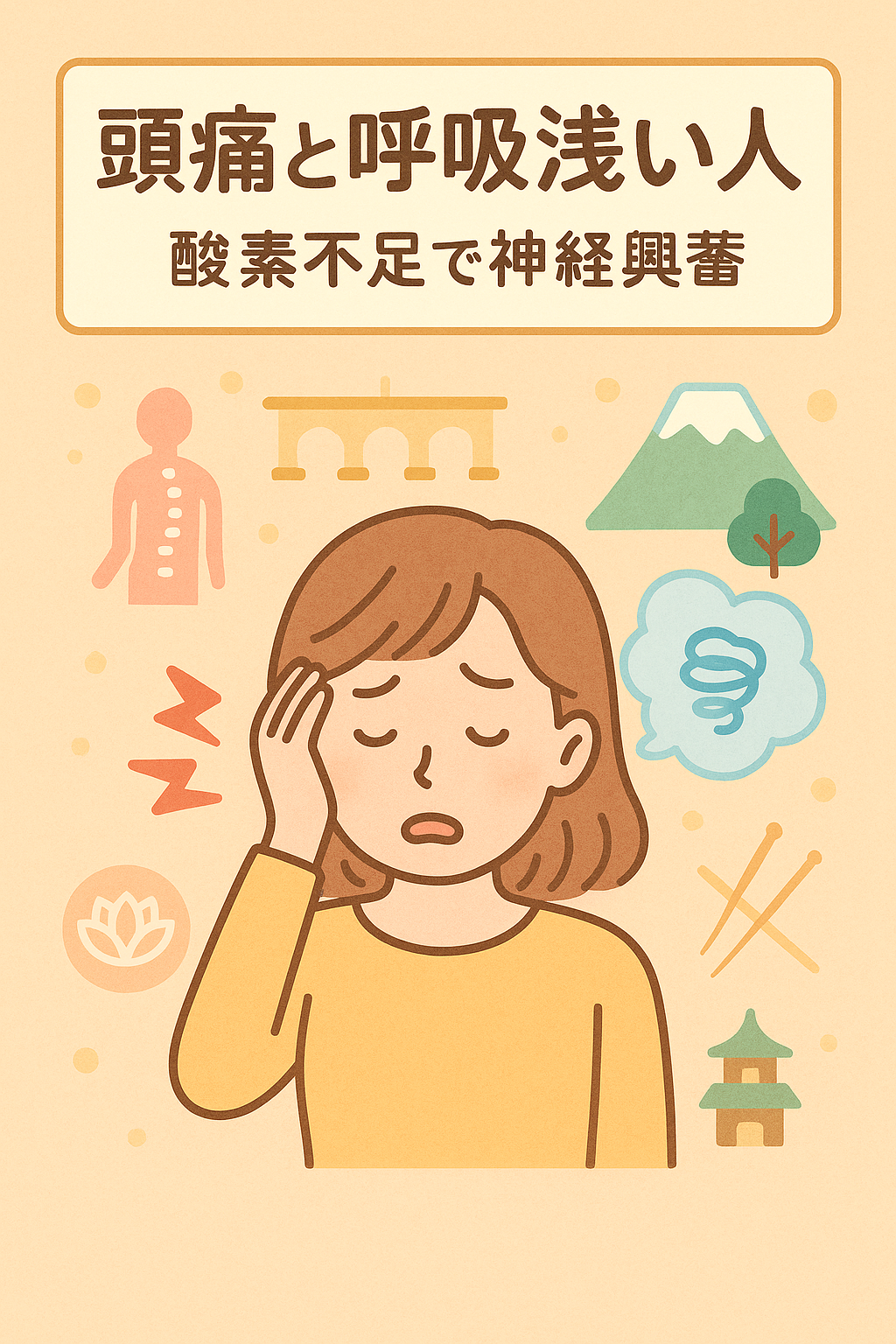
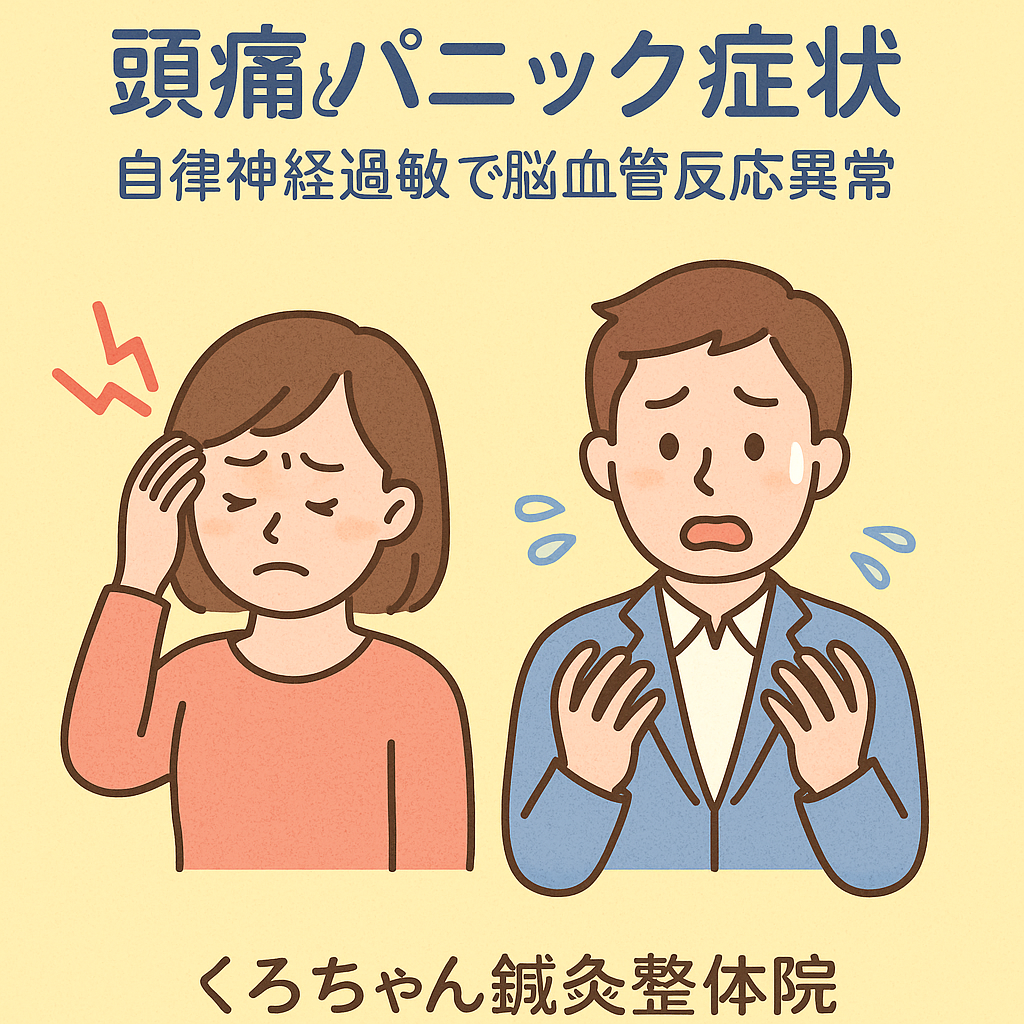

コメント