はじめに
夏場や気温の高い季節になると、熱中症対策として「水分をこまめに取りましょう」とよく言われます。しかし、頻尿が増えてしまうと必要な水分が体内に留まりにくくなり、体温維持が難しくなることがあります。特に、脱水気味の状態でさらに尿として水分を失うと、体温が急上昇しやすく、熱中症の危険が高まります。
このような状態の背景には、自律神経の乱れが深く関わっている場合が多く、さらに東洋医学的には腎や膀胱の働きの低下が関与していると考えられます。この記事では、頻尿と体温維持の関係、そして自律神経・東洋医学的な視点からの改善法、さらにくろちゃん鍼灸整体院での具体的な施術方法について詳しく解説していきます。
頻尿と体温維持の関係
頻尿とは、昼間に8回以上、または夜間に2回以上トイレに行く状態を指すことが多く、加齢や泌尿器の疾患だけでなく、自律神経の不調、ホルモンバランスの乱れ、精神的ストレスなどでも起こります。
特に夏場に頻尿が悪化すると、体温調節機能に次のような影響を与えます。
- 体内の水分不足
尿として水分を排出することで、発汗に必要な体液量が減少し、放熱効率が低下します。 - 皮膚血流の低下
脱水により血液が濃縮し、末梢血流が減少するため、熱を逃しにくくなります。 - 発汗機能の低下
体は水分不足を察知すると、発汗量を抑制しようとするため、熱が体内にこもりやすくなります。
このように、頻尿による水分喪失は体温調節システムにダイレクトな悪影響を与えるのです。
自律神経から見る頻尿と熱中症の関係
自律神経は交感神経と副交感神経のバランスによって成り立っています。交感神経は活動や緊張時に働き、副交感神経は休息や回復時に働きます。膀胱の機能は、この自律神経の調節に大きく依存しています。
- 交感神経の過剰興奮
尿をためる機能(蓄尿)は交感神経が優位な時に保たれますが、過剰な緊張が続くと膀胱の感受性が高まり、少量の尿でも排尿反射が起きやすくなります。 - 副交感神経の乱れ
排尿は副交感神経が優位な時に起こりますが、この切り替えがうまくいかないと、日中や夜間に不必要な排尿が増えます。
この自律神経の乱れが頻尿を悪化させ、さらに体温調節の中枢である視床下部にも影響を与えるため、熱中症リスクが高まります。
東洋医学的な頻尿と体温不安定の解釈
東洋医学では、頻尿や体温維持の難しさは「腎虚」「脾虚」「膀胱気虚」などの証と関連します。
- 腎虚(じんきょ)
腎は水分代謝と精の蓄えを司ります。腎の働きが弱ると、体液を保持できず、頻尿や夜間尿が増加します。体を温める「命門の火」も弱まり、体温維持が困難になります。 - 脾虚(ひきょ)
脾は食物から得た水穀の精微を全身に送る役割があります。脾の機能が低下すると水分が適切に代謝されず、体に必要な潤いが不足しやすくなります。 - 膀胱気虚(ぼうこうききょ)
膀胱を引き締める力が弱まり、尿が漏れやすくなります。気の不足は発汗や体温保持にも影響します。
東洋医学では、これらを調整することで頻尿を減らし、体温維持力を高めることが可能です。
くろちゃん鍼灸整体院での施術アプローチ
骨盤矯正
骨盤は膀胱や腎臓を支える土台であり、骨盤のゆがみが尿意の感覚や膀胱の位置に影響します。骨盤矯正により、下腹部の血流が改善し、自律神経の働きも安定します。
猫背矯正
猫背姿勢は内臓を圧迫し、骨盤や膀胱周囲の神経を刺激します。姿勢を正すことで尿意のコントロールがしやすくなり、同時に胸郭が開くことで体温調節のための呼吸がスムーズになります。
鍼灸施術
東洋医学の視点から腎兪・膀胱兪・関元・三陰交などのツボを用い、腎気を補い膀胱の機能を整えます。自律神経を調整するツボ(百会・内関など)を併用し、排尿と体温維持の両面から改善を図ります。
頭部施術
頭部には自律神経中枢をリラックスさせるポイントがあります。頭部の緊張を緩めることで、排尿のリズムと体温調整機能の両方が安定しやすくなります。
通院の目安
- 急性期:週2回の集中ケア
- リハビリ期:週1回の調整
- メンテナンス期:月2〜3回の体調管理
予約方法
くろちゃん鍼灸整体院では、LINE予約・ホームページから24時間予約受付中です。急な体調変化にも対応できるよう、柔軟な予約枠をご用意しています。
✅ LINE・ホームページから24時間予約受付中
今すぐご予約はこちらから!相談も予約もLINEでのご連絡が便利です!
📱LINE![]()





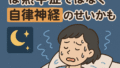
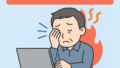
コメント