「最近、尿がにごっている…」それ、東洋医学では“小腸湿邪”が原因かもしれません。
尿のにごりや違和感は、膀胱や腎の問題と捉えがちですが、東洋医学では「小腸湿邪(しょうちょうしつじゃ)」という病理が関係していることがあります。
この湿邪は小腸の機能を阻害し、排尿機能に異常を生じさせるだけでなく、全身の不快症状につながることも。
◆ 小腸湿邪とは?東洋医学の視点から詳しく解説
東洋医学における小腸の主な役割は「受盛(じゅせい)と化物(けぶつ)」、つまり胃から送られた飲食物をさらに分別し、清(せい)を体内に、濁(だく)を尿として排出する役割があります。
しかし、体内に湿邪が侵入し小腸に停滞すると、以下のようなトラブルが起こります:
- 小腸の清濁分別作用が弱まり、濁りのある尿が生じる
- 排尿時ににごり・粘り・熱感が出る
- 下腹部の重だるさや違和感
- 食欲不振・吐き気・口内のねばつきなど、消化器症状も併発
- 舌苔が白く厚くなり、舌がむくむ
湿邪は「重く停滞しやすい」性質を持ち、冷たい飲食物・長時間の座り仕事・エアコン環境などで体内に溜まりやすくなります。
◆ 当院での施術アプローチ
くろちゃん鍼灸整体院では、小腸湿邪による排尿トラブルに対し、以下の4つの視点でアプローチします。
▶ 骨盤矯正:下焦の水分代謝改善
骨盤周囲の歪みは、腎・膀胱・小腸の経絡の流れを滞らせる原因となります。
骨盤矯正によって経絡の流れ・血流・リンパ循環を改善し、体内の湿邪が排出されやすい状態を整えます。
▶ 猫背矯正:胸腹部の内臓機能を活性化
猫背によって前屈みの姿勢が続くと、内臓が圧迫され、小腸の働きが低下します。
猫背矯正で正しい姿勢を取り戻すことで、小腸の清濁分別機能を高め、排尿の透明感や勢いの回復が期待できます。
▶ 鍼灸施術:小腸経・膀胱経・脾経へのアプローチ
- 【使用経穴例】小腸兪、水分、関元、陰陵泉など
- 湿邪を排出するために、脾の運化力を補いながら水分代謝を改善
- 小腸・膀胱の熱や湿を抜くことで、尿の濁りや頻尿、不快感を解消に導きます
鍼灸は自律神経とホルモンバランスの調整にも有効で、排尿トラブルの根本改善につながります。
▶ 頭部施術:脳のストレス解放と水分コントロールの調整
頭部へのアプローチで、自律神経のバランスを整えると下焦の水液代謝機能も改善されやすくなります。
また、不眠やストレス性の排尿異常にも対応できます。
◆ 通院の目安と予約方法
| 期間 | 頻度 | 内容 |
|---|---|---|
| 急性期 | 週2回 | 排尿異常や尿のにごりが強い状態を早期改善 |
| リハビリ期 | 週1回 | 内臓の機能と姿勢の安定化 |
| メンテナンス期 | 月2〜3回 | 湿邪の再発予防と体質改善 |
ご予約は【LINE】または【ホームページ】から24時間受付中です。
✅ LINE・ホームページから24時間予約受付中
今すぐご予約はこちらから!相談も予約もLINEでのご連絡が便利です!
📱LINE![]()



◆ 小田原市・くろちゃん鍼灸整体院からのご案内
小腸湿邪による尿のにごりや排尿トラブルは、湿度が高い季節・冷たい飲食物の摂取・過労・ストレスによって悪化することがあります。
慢性化する前に、東洋医学に基づく整体と鍼灸で体質から見直していきましょう。


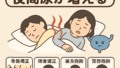
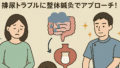
コメント