くろちゃん鍼灸整体院(小田原市)ブログ記事
はじめに
「足先が冷たくて眠れない」「冷え性で冬だけでなく夏も足が冷たい」という方は多いですよね。そんな方の中には、「足が冷えているのに頭が痛い」「足が冷えると頭がぼーっとして重い」といった症状を訴えるケースもあります。
実はこれ、“下半身冷え”によって頭の血管が拡張し、頭痛を引き起こしていることがあるのです。今回は、足の冷えと頭痛の関係、自律神経の仕組み、東洋医学の観点、そしてくろちゃん鍼灸整体院での具体的な施術方法についてお話しします。
下半身の冷えが頭痛を引き起こすメカニズム
● 体温バランスの乱れが血管を拡張させる
人間の体は「頭寒足熱(ずかんそくねつ)」が理想とされています。つまり、頭は適度に涼しく、足は温かい状態が健康的です。しかし、冷え性や長時間のデスクワーク、運動不足、薄着などにより下半身が冷えると、体は“熱を逃がさないように”と血流を上半身に集中させます。
結果的に、頭部の血流が過剰になり、血管が拡張。これが「ズキズキ」「ガンガン」といった拍動性頭痛(片頭痛型)の原因になるのです。
● 自律神経の働きがアンバランスに
体温や血管の拡張・収縮は、自律神経によってコントロールされています。冷えによって交感神経が緊張しすぎると、血管の収縮が強まり、末端(足先)への血流が減少。逆に、反動として頭部では副交感神経が優位になり、血管が拡張します。
この“上下の自律神経アンバランス”が、頭痛や頭重感を悪化させる要因になります。
東洋医学から見た「冷え」と「頭痛」の関係
東洋医学では、冷えは「気血の巡りの滞り」として捉えます。特に下半身が冷える場合、次のようなタイプが考えられます。
- 腎陽虚(じんようきょ):体を温める力が弱まり、慢性的な冷えや腰のだるさを伴うタイプ。
- 気虚(ききょ):エネルギー不足により血流を押し出す力が弱いタイプ。
- 血瘀(けつお):血の流れが滞って冷えと痛みを同時に起こすタイプ。
このような冷えが進行すると、「上熱下寒(じょうねつかかん)」といって、上半身(特に頭部)は熱がこもり、下半身は冷えた状態になります。まさにこの状態が「足が冷えると頭が痛くなる」メカニズムです。
くろちゃん鍼灸整体院での施術アプローチ
● 骨盤矯正で血流の基盤を整える
骨盤の歪みは下半身の血流を妨げる大きな原因です。骨盤が傾くと、太ももやふくらはぎの筋肉が緊張し、血液やリンパの流れが滞ります。くろちゃん鍼灸整体院では、やさしい手技による骨盤矯正で足の血流を促進し、冷えにくい体のベースを整えます。
これにより、頭部の過剰な血流も落ち着き、頭痛の緩和につながります。
● 猫背矯正で自律神経の通りを良くする
猫背姿勢では背骨の中を走る自律神経が圧迫され、交感神経・副交感神経の切り替えがうまくいかなくなります。特に首〜背中の丸まりは「頭痛+冷え」を悪化させる原因になります。
猫背矯正によって胸を開き、背骨のラインを整えることで、自律神経の流れがスムーズになり、血流バランスが自然に戻っていきます。
● 鍼灸施術で自律神経と血流をダブル調整
冷えや頭痛に対しては、足の「三陰交(さんいんこう)」や「太谿(たいけい)」などの温めのツボ、そして頭の「百会(ひゃくえ)」や「風池(ふうち)」といった頭痛ポイントに鍼灸を行います。
鍼で筋肉をゆるめ、灸で深部を温めることで、足元の血流改善と頭部の血管拡張の抑制を同時に叶えます。これにより、自律神経のリズムが整い、冷えも頭痛も根本的に改善します。
● 頭部施術で脳の血流を安定化
頭皮・後頭部・首筋を丁寧にほぐすことで、過度に拡張した血管を落ち着かせ、脳の圧迫感を軽減します。特に、側頭部や後頭下筋群の硬直は「冷えからくる頭痛」を長引かせる原因。
頭部施術を行うことでリラックス神経(副交感神経)が働き、睡眠の質も改善されます。
日常生活でできる冷え&頭痛対策
- 足湯や温かい靴下で「足を冷やさない」
- スマホ・PC作業の合間に「足首回し」や「つま先立ち運動」
- 寝る前は冷たい飲み物を避け、「白湯」や「生姜湯」がおすすめ
- 骨盤や背中を丸めすぎない姿勢を意識
通院の目安
- 急性期(症状が強い時期):週2回
- リハビリ期(安定してきた時期):週1回
- メンテナンス期(再発予防):月2〜3回
冷えと頭痛は一時的な対症療法ではなく、体質改善が重要です。定期的なケアで、冷えに強く、頭痛知らずの体をつくっていきましょう。
ご予約・お問い合わせ
くろちゃん鍼灸整体院では、
LINE・ホームページで24時間予約受付中!
施術者が一人のため、予約が取りづらくなっております。お早めにご連絡ください。
✅ LINE・ホームページから24時間予約受付中
今すぐご予約はこちらから!相談も予約もLINEでのご連絡が便利です!
📱LINE![]()





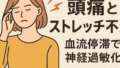
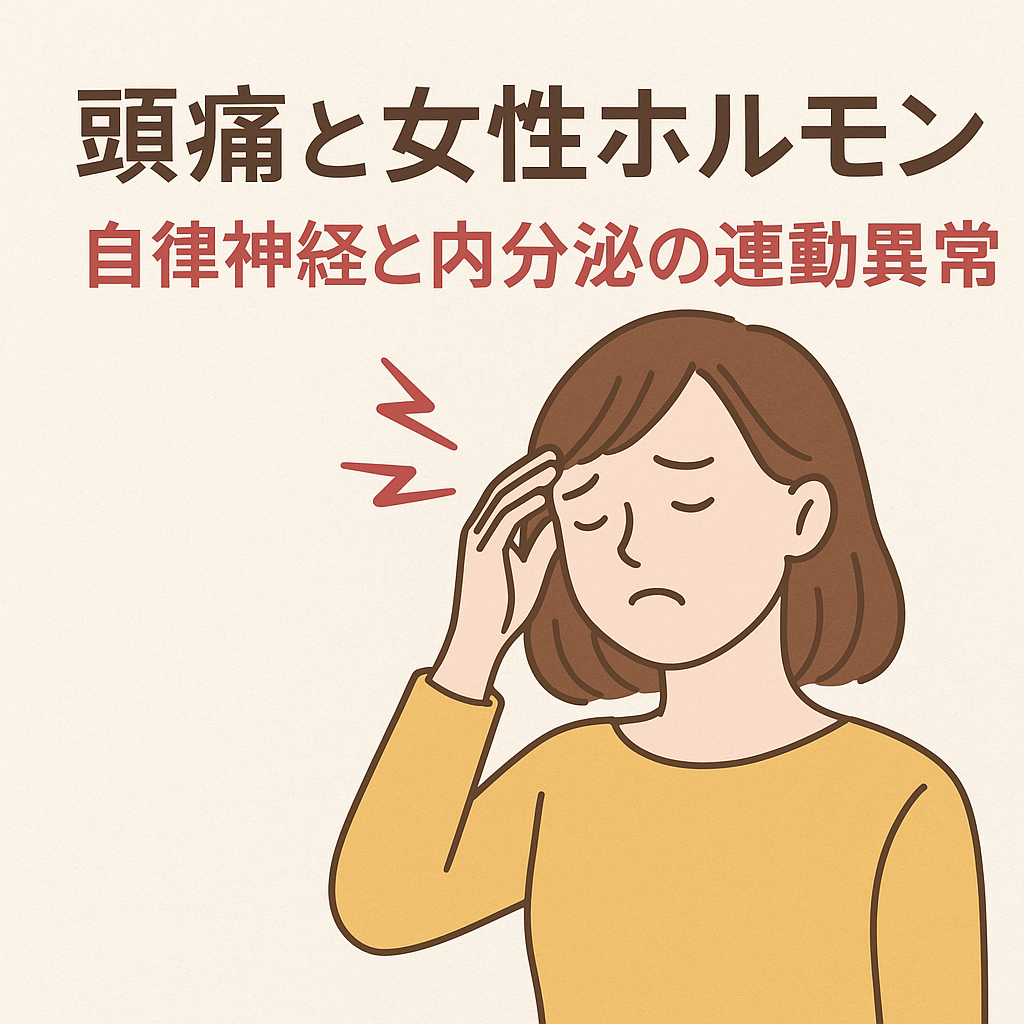
コメント