はじめに
「夜中に心臓がドキドキして目が覚める」「眠っているのに息苦しくて飛び起きる」――そんな経験はありませんか?
実はそれ、自律神経のスイッチが誤作動を起こしているサインかもしれません。夜は本来“副交感神経”が優位になり、体を休める時間。しかし、ストレスや姿勢の乱れ、冷え、神経の緊張によって、夜中でも“交感神経”が働き続けてしまうことがあります。
この記事では、夜の動悸の原因を「自律神経」と「東洋医学」の両面からわかりやすく解説し、くろちゃん鍼灸整体院で行っている施術(骨盤矯正・猫背矯正・鍼灸施術・頭部施術)がどのように改善を助けるのかを詳しくお伝えします。
夜の動悸が起こるメカニズム
夜の動悸は「交感神経の誤作動」によって起こります。日中に強い緊張状態が続くと、夜になっても脳が“戦闘モード”から抜け出せず、心臓や呼吸を司る神経が働き続けてしまうのです。
特に、こんな状態が続く方は要注意です。
- 寝る直前までスマホやPCを見ている
- 考えごとが多く、眠りが浅い
- 体が冷えている、または寝汗をかきやすい
- 姿勢が悪く、胸郭や首回りが硬い
これらの習慣は、脳の視床下部にある自律神経の切り替えスイッチに影響を与え、「夜も交感神経が優位なまま」の状態を引き起こします。
東洋医学から見た夜の動悸
東洋医学では、夜の動悸は「心(しん)」と「腎(じん)」のバランスの乱れと考えます。
- 心(しん):血液の循環や精神の安定を司る臓腑
- 腎(じん):生命エネルギーや深い眠りを支える臓腑
ストレスや疲労、冷えなどで腎の力が弱まると、心を落ち着ける力も低下し、夜に“気”が上に上がってしまうため、動悸や不安、浅い眠りが起こりやすくなります。
また、胸のあたりの「気滞(きたい)」、つまり気の流れの滞りも大きな原因です。特に秋冬の寒暖差や気圧変化の激しい時期には、体表の気が縮こまり、胸の内側で気がこもりやすくなります。これが夜のドキドキや息苦しさを誘発します。
骨盤矯正による神経スイッチの安定
骨盤は、全身の自律神経バランスを整える“基盤”です。骨盤が歪むと背骨がねじれ、背骨を通る自律神経(特に交感神経)が常に刺激される状態になります。
くろちゃん鍼灸整体院では、優しい矯正で骨盤の傾きを整え、仙骨周辺にある副交感神経の働きを引き出します。これにより、
- 夜に心臓がドキドキしにくくなる
- 深呼吸がしやすくなる
- 眠りが深くなる
といった変化が現れます。
猫背矯正で呼吸と血流を改善
猫背の方は胸郭(胸のかご状の部分)が狭くなり、心臓や肺を圧迫しています。その結果、呼吸が浅くなり、酸素不足によって交感神経が過敏になります。
猫背矯正では、肩甲骨や胸椎の可動域を広げて呼吸を深くし、血流を改善。胸部の圧迫を取り除くことで、自然と夜間の動悸も減っていきます。
鍼灸施術で心身の緊張をほどく
鍼灸では、「心包経」「神門」「内関」などのツボを中心に、心の高ぶりや不安感を鎮める施術を行います。
また、背中の「膈兪(かくゆ)」や「心兪(しんゆ)」といったツボに鍼を打つことで、胸部の血流と自律神経の切り替えをスムーズにします。さらにお灸で「腎兪(じんゆ)」を温めると、冷えによる夜間の動悸が和らぎます。
鍼灸の効果は単なるリラックスではなく、脳の視床下部を介して交感神経と副交感神経のバランスを整える科学的な側面もあります。
頭部施術で脳の興奮をリセット
夜中に動悸が出る方は、脳が「夜でも昼モード」のままになっていることが多いです。頭皮やこめかみ周辺の筋肉が硬く、脳血流が滞ると、自律神経の切り替え信号が乱れます。
頭部施術では、頭皮の筋膜をゆるめて血流を改善。脳に「安心して眠っていいですよ」という信号を送ることで、自然な眠りを取り戻していきます。
通院の目安
症状の程度により異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。
- 急性期(症状が強い時):週2回
- リハビリ期(安定してきたら):週1回
- メンテナンス期(再発予防):月2〜3回
夜の動悸は、焦らずじっくり整えていくことが大切です。神経のクセは時間をかけて修正することで、再び“夜は眠れる体”を取り戻せます。
まとめ
夜の動悸は「心の問題」だけでなく、「体の神経スイッチの誤作動」が関係しています。姿勢の乱れや骨盤の歪み、血流の滞りが積み重なると、夜でも交感神経が働き続けてしまいます。
くろちゃん鍼灸整体院では、
- 骨盤矯正で神経の通りを整え
- 猫背矯正で呼吸を深め
- 鍼灸施術で心身の緊張を解き
- 頭部施術で脳をリラックス状態に導く
という総合的なアプローチで、あなたの夜の安らぎを取り戻します。
【*効果には個人差があります】
✅ LINE・ホームページから24時間予約受付中
今すぐご予約はこちらから!相談も予約もLINEでのご連絡が便利です!
📱LINE![]()





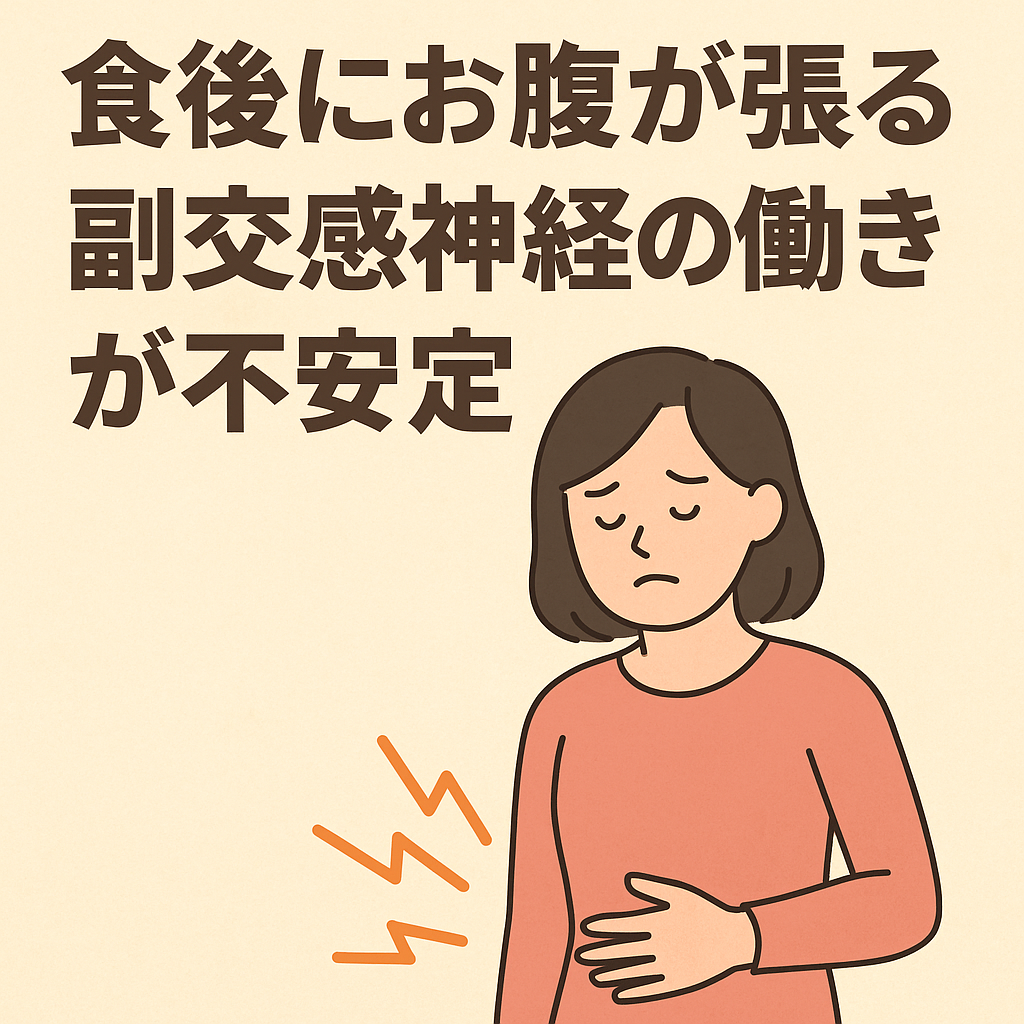

コメント